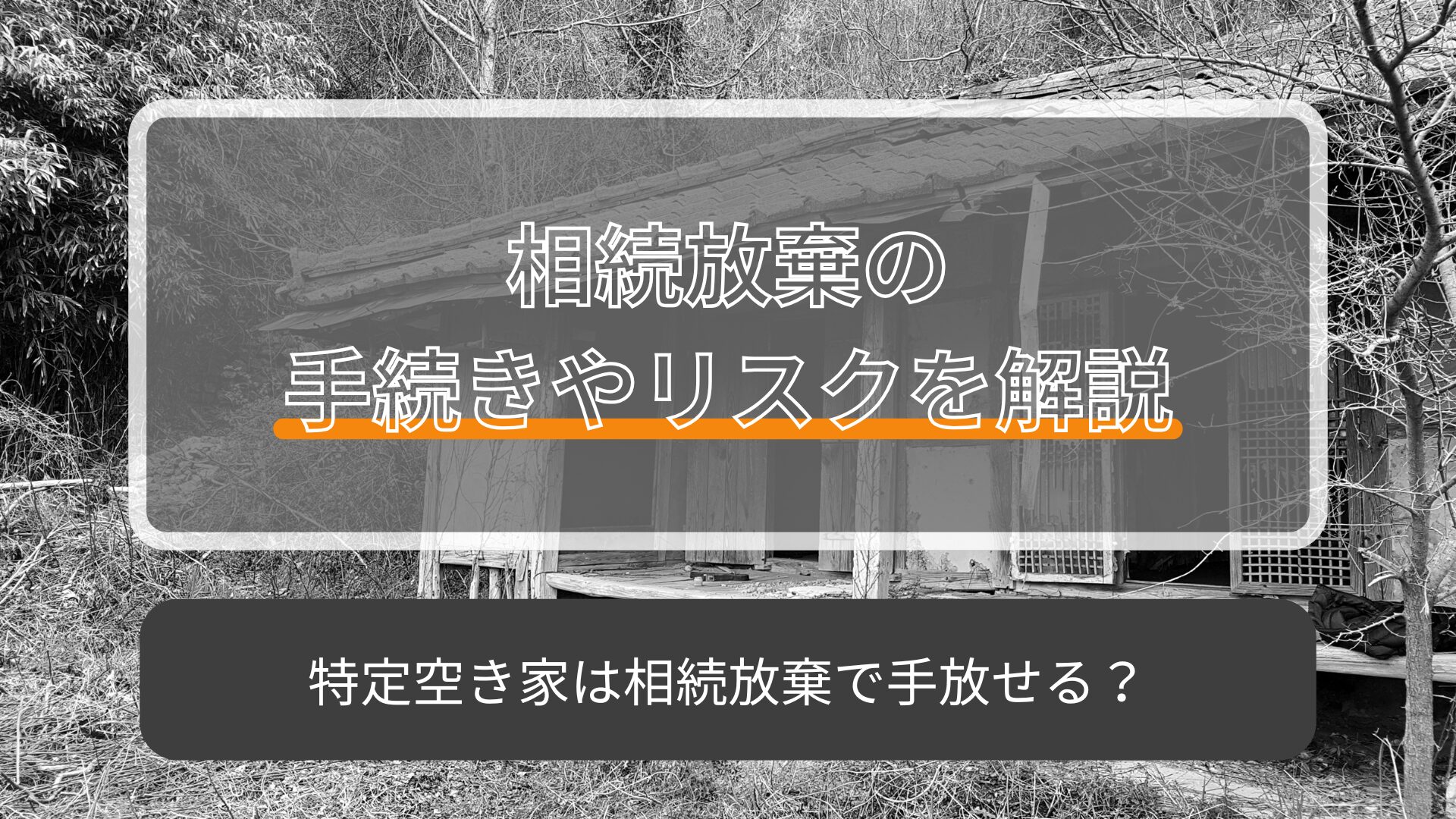「管理しきれない古い実家は、相続放棄すれば手放せる?」と悩んでいる方もいるでしょう。特定空き家に指定されると支払う税金や修繕費が増え、行政から命令や代執行のリスクがあり、所有し続けるのは負担が大きいです。
たとえば老朽化したまま放置して「特定空き家」に認定されると、住宅用地の税優遇が外れ、固定資産税が6倍になるケースがあります。行政の命令や代執行が行われると、費用は所有者が負担しなくてはいけません。
- 特定空き家に指定されるリスクとその影響
- 相続放棄のメリット・デメリット
- 相続放棄しない場合の現実的な空き家対処法
この記事では、特定空き家のリスクや相続放棄の手続き方法まで詳しく解説します。「空き家を放棄するかどうか迷っている」「損せず安全に処理したい」と考えている方にとって、どうするべきかの判断材料になる情報が満載です。ぜひ最後までご覧ください。
特定空き家とは周囲に悪影響を及ぼす恐れのあると行政が指定した空き家
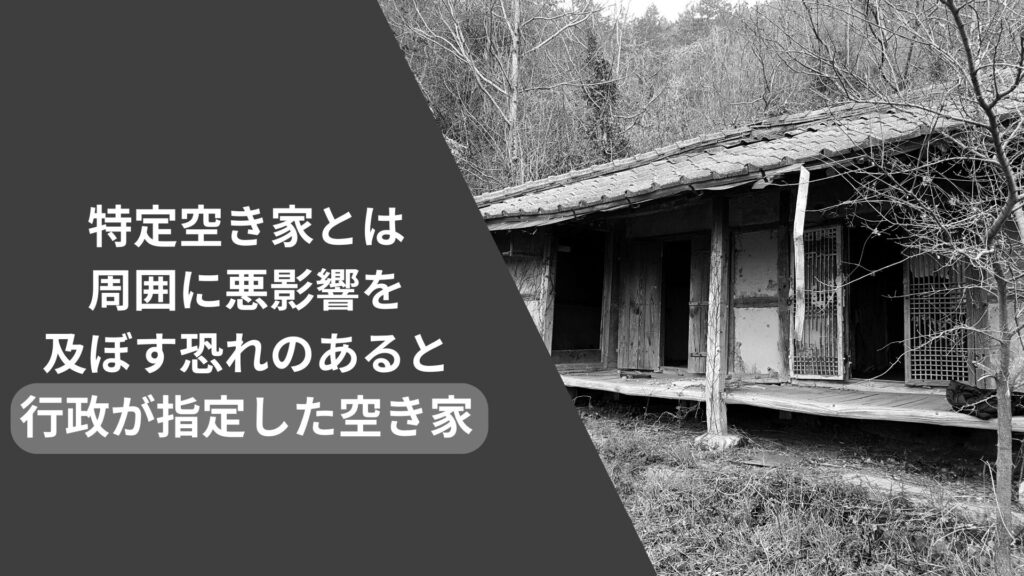
特定空き家とは、老朽化や管理不足により、周囲の住環境に悪影響を及ぼすと市区町村から判断された空き家のことです。
(空家等対策の推進に関する特別措置法 第2条2項)
この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
具体的には、以下のような状態にある空き家が対象です。
- 倒壊や屋根の落下など、安全面での危険がある
- ゴミの放置やカビ・害虫の発生など、衛生面に悪影響を与えている
- 草木が伸び放題、外壁が崩れているなど、景観を著しく損ねている
- 近隣住民の暮らしに支障をきたす恐れがある
市町村から指定を受けると、住宅用地の特例の対象外となり、税負担が増える可能性があります。所有者に対して修繕や撤去などの勧告・命令が出され、最終的には行政による強制的な解体(代執行)とその費用請求が行われることがあります。
特定空き家を相続放棄する3つのメリット

空き家をそのまま引き継ぐと管理や税金など多くの負担が発生し、特定空き家に指定されたら法的なリスクも高まります。相続放棄をすることで、所有者としての責任から解放され、トラブルを未然に防ぐことが可能です。ここでは、相続放棄によって得られる主なメリットを3つ解説します。
- 行政からの解体命令や代執行を免れる
- 固定資産税の支払いを免れる
- 倒壊・火災などによる損害賠償リスクを回避できる
行政からの解体命令や代執行を免れる
特定空き家に指定されても放置が続いた場合、自治体から命令が出され、最終的には行政代執行されることがあります。命令や代執行は空家等対策特別措置法に基づいて行われ、費用はすべて所有者の負担です。
市町村長がする命令は重い措置であり、違反すると50万円以下の過料が科せられます。命令に従わずに特定空き家を放置すると、行政代執行の対象となります。支払いを拒否すると、不動産が差し押さえられる可能性もあるため注意が必要です。
命令や代執行を回避する手段のひとつが、相続放棄です。放棄すれば空き家の所有者ではなくなるため、命令や代執行の対象から外れます。
固定資産税の支払いを免れる
空き家は使っていなくても、所有している限り毎年固定資産税が課税されます。都市部では、固定資産税が年間で数十数万円の負担になることも珍しくありません。
特定空き家に指定され「勧告」を受けた場合は、税の優遇措置である住宅用地の特例が解除されます。小規模住宅用地に該当する場合は、評価額の6分の1に軽減されているため、特例が適用されなくなると現在の固定資産税は6倍になるケースがあります。
「誰も住まない実家に毎年税金を払い続けるのは避けたい」「老朽化して売ることもできない」といった場合は、相続放棄が現実的な選択肢となり得ます。相続放棄をすれば、空き家を正式に引き継がないことになるため、こうした税負担からも解放されます。
倒壊・火災などによる損害賠償リスクを回避できる
老朽化が進んだ空き家を放置していると、台風や地震などの自然災害で屋根や外壁が崩れ、近隣の住宅や通行人に被害を与えてしまうおそれがあります。被害が発生すれば、適切に管理していなかったとして、相続人が損害賠償を請求されるケースがあります。
建物に不具合がなくても、放置されている空き家は放火や不法侵入といった犯罪の温床になりやすく、火災が発生すれば周囲への延焼リスクもあります。草木が伸び放題であれば、虫が大量発生して生活環境が悪化するので、近隣住民からの苦情がきます。
相続を放棄すれば空き家の所有者ではなくなるため、管理責任や損害賠償のリスクを回避できます。
特定空き家を相続放棄する3つのデメリット

実は相続放棄を選んだことで別のトラブルが生じたり、大切な財産を失ってしまったりする可能性があります。ここでは、特定空き家を相続放棄する際に注意すべきデメリットを3つ解説します。
- 放棄しても管理義務が残る可能性がある
- 他の相続財産も引き継げなくなる
- 他の相続人との関係性に影響が出ることがある
放棄しても管理義務が残る可能性がある
相続放棄をすれば、空き家に関するすべての責任から解放されると考えている方は少なくありません。しかし、相続放棄をしても一時的に管理義務が残るケースがあります。
2023年4月に民法が改正され、相続財産を現に占有している者が引き渡しまでの間に保存義務を負うと明記されています。現に占有しているとは、国土交通省の資料によると以下のような状況です。
- 実際に住んでいる
- 建物内に物を置いている
- 建物の鍵を持ってる
このようなケースでは占有と見なされる可能性があり、管理責任が問われる恐れがあります。相続放棄をする際には必要に応じて弁護士などの専門家に相談し、放棄後のリスクを正しく理解したうえで行動することが大切です。
他の相続財産も引き継げなくなる
相続放棄は、はじめから相続人でなかったとみなされる手続きです。相続人としてのすべての権利を放棄することになり、以下のようなプラスの財産も受け取れません。
- 預貯金
- 株式や投資信託などの金融資産
- 不動産
- 美術品
- 貴金属
- 自動車
相続放棄して「空き家はいらないけれど、預金だけは欲しい」ということはできません。すべての財産を対象とするものであり、財産ごとに取捨選択はできない点に注意が必要です。
また、放棄した後に「実は隠れた不動産や多額の預金があった」と判明しても、一度放棄したら撤回はできません。相続放棄を検討する際は「空き家がいらない」という理由だけで即決するのではなく、全ての財産を調査してプラスとマイナスを見極めたうえで判断することが大切です。
他の相続人との関係性に影響が出ることがある
相続する権利には優先順位があり、第1順位である子ども全員が相続放棄をすると、第2順位の両親、第3順位の兄弟姉妹へと移ります。後順位の相続人に放棄の事実を伝えないと、金融機関や債権者から通知を受けて「自分が相続人になっていた」と知ることになります。
思わぬ形で空き家の相続人になった場合、突然管理の負担を強いられ家族や親族間の信頼関係にヒビが入ってしまうこともあります。相続放棄をする際は、他の相続人へ連絡する法律上の義務はありません。しかし、事前に放棄の意思を共有し、協議しておくと不満や対立を避けられます。
相続は「法的な手続き」だけでなく、「家族の問題」でもあるという視点を持つことが重要です。
特定空き家を相続放棄する方法

実際に放棄するためには、相続財産の調査から裁判所への申立てまで、何をいつまでに行うべきかを確認しておきましょう。ここでは、相続放棄の流れを3つのステップに分けてわかりやすく解説します。
- 相続財産を調査する
- 「相続放棄申述書」を作成する
- 「相続放棄申述受理通知書」を受領する
相続財産を調査する
空き家のような不動産だけでなく、預貯金や株式などのプラスの資産、借金や未払金などのマイナスの負債も含めてすべてが「相続財産」です。被相続人の遺産の全てを正しく把握しましょう。「相続放棄をすることで損をしないか」を見極めることが重要です。
相続放棄は一度行うと原則として撤回できないため、空き家がいらないという理由だけで安易に判断してはいけません。後になって預金があることが判明し、後悔する可能性があります。財産の調査は、以下の資料が役立ちます。
- 預金通帳
- 保険証券
- 保有株式の明細
- 固定資産税通知書
- 借入契約書
契約書や証書などの重要書類だけでなく、郵便物やメールも財産の確認に有効です。
「相続放棄申述書」を作成する
相続財産の内容を確認し相続放棄を決めたら、次は家庭裁判所へ提出する書類を作成します。相続放棄申述書と記載例は、裁判所のホームページにあるので参考にしてください。申述書は、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ提出しなければなりません。申述書以外に必要な主な書類は、以下のとおりです。
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 被相続人の死亡記載のある戸籍謄本
- 申述人(相続を放棄する人)の戸籍謄本
- 800円分の収入印紙
- 郵便切手(裁判所によって金額が異なる)
必要書類は相続順位によって追加される場合があるため、不明な点は事前に裁判所へ確認しておくと安心です。
「相続放棄申述受理通知書」を受領する
相続放棄申述書を提出すると、家庭裁判所から「照会書(質問票)」が届きます。
照会書には「なぜ相続放棄を希望するのか」「相続財産を使っていないか」などの質問があり、正確に回答して返送しなくてはいけません。照会書の内容によっては相続放棄が認められないことがあるため、曖昧であれば弁護士などの専門家へ相談するのが賢明です。
照会書を返送後、家庭裁判所の審査を経て問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が郵送されます。通知書を受け取った時点で、正式に相続放棄が認められた状態です。
通知書は他の相続人や債権者とのやり取りに使うこともあるため、大切に保管しておきましょう。必要に応じて、裁判所で「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらうこともできます。
特定空き家を相続放棄する注意点

特定空き家の相続放棄には手続きの期限があり、進める上でいくつか注意すべき点があります。ここでは、相続放棄を検討するうえで、失敗しやすいポイントを解説します。
- 相続放棄できる期限が決められている
- 占有していると相続放棄が認められない可能性がある
相続放棄できる期限が決められている
相続放棄には「熟慮期間」と呼ばれる期間があり、相続が始まったことを知った日から3ヶ月以内と法律で定められています。相続放棄するまでの3ヶ月で行うべきことは、主に以下のとおりです。
- 遺言書の有無を確認する
- 相続人としての立場を把握する
- 財産や負債の内容を調査する
- 家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する
申述書の提出が3ヶ月を過ぎてしまうと、自動的にすべての財産と負債を引き継ぐ「単純承認」とみなされる可能性があるため注意が必要です。
ただし、期限後であっても、相続放棄するかを決められなければ家庭裁判所に申し立てることで、熟慮期間を伸長することが可能です。
民法915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
相続放棄を検討している方は、期限が3ヶ月であることを意識し、早めの行動と正確な情報収集を心がけましょう。
占有していると相続放棄が認められない可能性がある
法律上「現に占有している」とみなされると、相続放棄をした後でも財産を保存する義務を負わなくてはいけません。占有とは、財産を事実上支配・管理している状態を指します。たとえば以下のケースが該当します。
- 放棄する家に住み続けている
- 放棄する家の鍵を持ち自由に出入りしている
- 放棄する家に自分の荷物を保管している
- 業者に放棄する家の清掃や修繕を依頼している
上記の行為があると、占有していると判断される可能性が高くなります。放棄の時点で相続財産を占有している場合、その財産を引き渡すまでの間は自己の財産と同様の注意をもって管理しなければいけません。さらに、積極的に管理・使用していた場合には、裁判所から「相続する意思があった」と判断され、相続放棄そのものが無効になる可能性もあります。
特定空き家を相続放棄しない場合の対処法3選
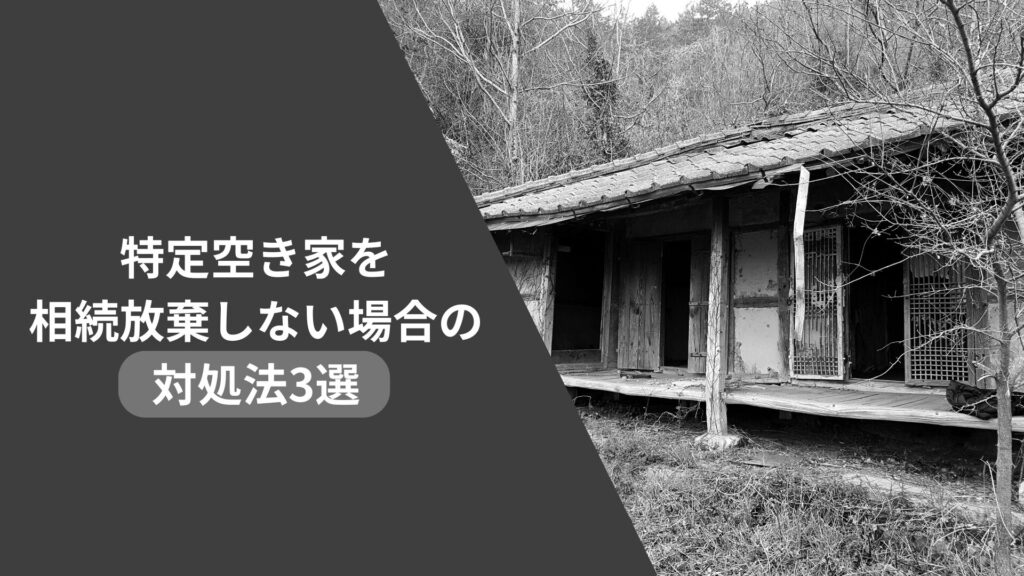
特定空き家に指定されると、行政からの勧告や命令を受ける可能性があり、放置すれば管理コストやリスクが増します。ここでは、相続放棄せずに不安を払拭できる、現実的な選択肢を3つ紹介します。
- 更地にして売却する
- 更地にして賃貸する
- 行政などに寄付する
更地にして売却する
空き家は建物の状態によっては買い手が付きづらく、売却までに期間がかかることがあります。築年数が経って特定空き家に指定されている場合、安全性の懸念や修繕コストを理由に購入が決まりにくくなります。しかし、更地にすれば以下のようなメリットがあります。
- 新築や駐車場など、用途の自由度が増す
- 買い手が解体費用を負担する必要がなく、購入希望者が増える
- 維持管理の手間やリスクを売却前に軽減できる
買い手にとって「すぐに活用できる土地」であることは、売却を決める重要な要素です。しかし、更地にするには建物の解体費用がかかります。一般的には木造住宅で100万~200万円程度が目安ですが、建物の構造や広さなどの条件によって変動します。
また、空き家を解体すると住宅用地の特例が対象外となるため、売却が長引くと固定資産税の負担が増す可能性があります。したがって、更地にして売却するのが向いているのは、以下のようなケースです。
- 建物が著しく傷んでおり、リフォームでは対応しきれない
- 立地条件がよく、土地としてのニーズが高い
- できるだけ早く確実に手放したい
多少の費用をかけてでも更地にすることで、結果的に早期の売却につながる可能性があります。
更地にして賃貸する
空き家を相続したけど売却するのは気が進まない方におすすめの方法が、空き家を更地にして土地を賃貸に出す方法です。建物を解体して更地にすれば、月極駐車場や資材置き場として活用されるケースが多く、一定の収益を見込めます。
賃貸であれば、売却して完全に手放すことなく、所有しながら有効活用できます。将来的に子どもが家を建てたい場合にも対応できるため、柔軟性が高い選択肢です。建物を解体することで倒壊リスクのある状態から脱却でき、特定空き家に指定される心配もありません。
一方で、解体には費用がかかり、更地での土地活用には管理や契約手続きが必要です。賃貸需要があるかどうか、地域のニーズを不動産会社に確認した上で、方針を決めることをおすすめします。
行政などに寄付する
特定空き家で売却が難しい場合、行政や公共団体への寄付を検討する方もいらっしゃるかもしれません。行政や公共団体によって定められた条件があるので、個別に確認してみましょう。しかし現実には、防災用地や公園などの公的な用途で使用できず管理コストがかかると判断され、寄付を受け入れるケースは少ないと言われています。
一方、国に土地を引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」を利用するという選択肢もあります。相続した土地であれば、単独でも共有でも申請が可能です。ただし、以下に該当するケースは対象外です。
- 建物がある
- 担保権などが設定されている
- 土地境界が明確でない
- 土壌汚染されている
また、申請できたとしても崖地で管理が大変な場合などは不承認されます。条件をすべて満たしても、審査の標準処理期間は8ヶ月とされ、時間がかかる場合があるため早期に空き家を手放したい方には不向きかもしれません。
まとめ:特定空き家の相続放棄は3ヶ月以内に決断する!
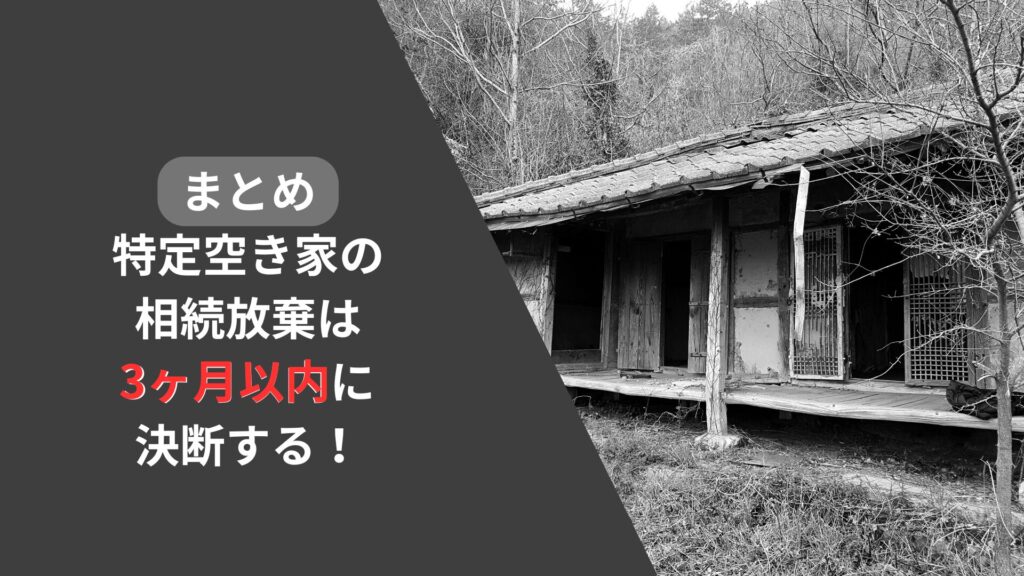
特定空き家に指定されると、固定資産税の優遇が外れるほか、行政から解体命令や代執行を受ける可能性があるため、適切な対処が求められます。相続放棄すれば、空き家の所有者にならずに済み、固定資産税の負担や損害賠償リスクを避けられます。しかし、他の相続財産を受け取れない、他の相続人との関係が悪化するおそれがあるなどのデメリットも存在します。
相続放棄は3ヶ月以内の申請期限があり、占有の状態があると放棄が認められない可能性もあるため、手続きには注意が必要です。
相続放棄を選ばない場合でも、更地にして売却したり、国庫帰属制度の利用など空き家の手放し方は複数あります。後悔しないために早めに家族で話し合い、専門家に相談しながら最適な選択肢を見つけることが大切です。