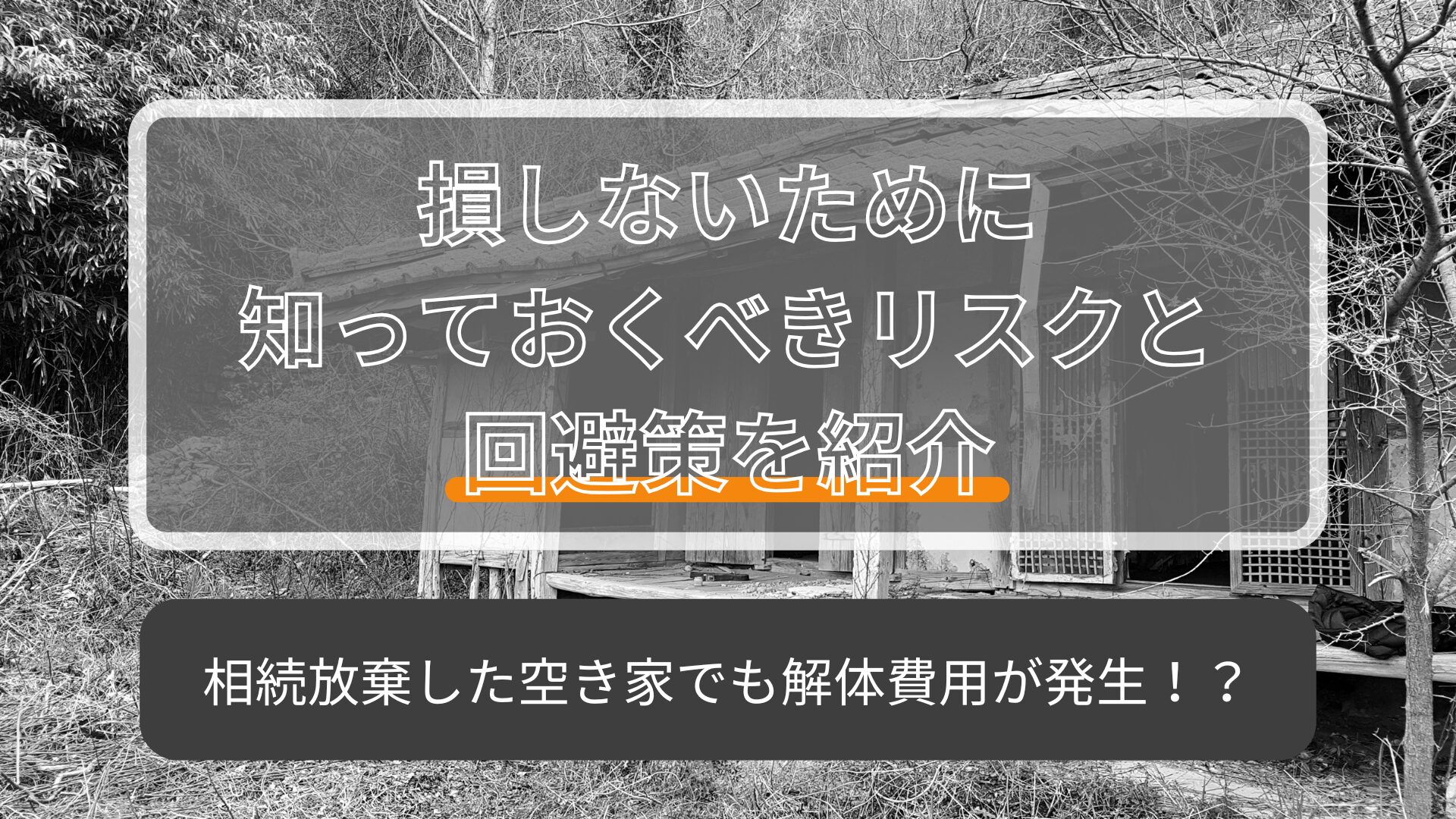親から相続した家が空き家になってしまった場合、「解体費用は誰が払うのだろう?」「相続放棄すればお金はかからないのでは?」と悩む方は少なくありません。老朽化した建物の解体には数百万円単位の費用がかかることもあり、負担の所在を誤解して思わぬトラブルに発展するケースもあります。
実は、相続放棄をしたとしても状況次第では解体費用や管理責任を負うことがあります。空き家を放置してしまうと「特定空き家」に指定され、税負担が増えたり行政による代執行で高額な費用を請求されたりするリスクも存在します。
この記事では、相続放棄と空き家の解体費用について、ケースごとの負担の違いや費用を軽減する方法などを分かりやすく解説します。空き家をめぐる費用と責任の仕組みを正しく理解し、損をしないための判断の参考にしてください。
- 相続放棄した空き家の解体費用を誰が負担するかは、ケースごとに異なる
- 解体費用を軽減・回避するための具体的な方法
- 空き家を解体しない・放置することによるリスク
【ケース別】空き家を相続放棄した際の解体費用は誰が負担するのか
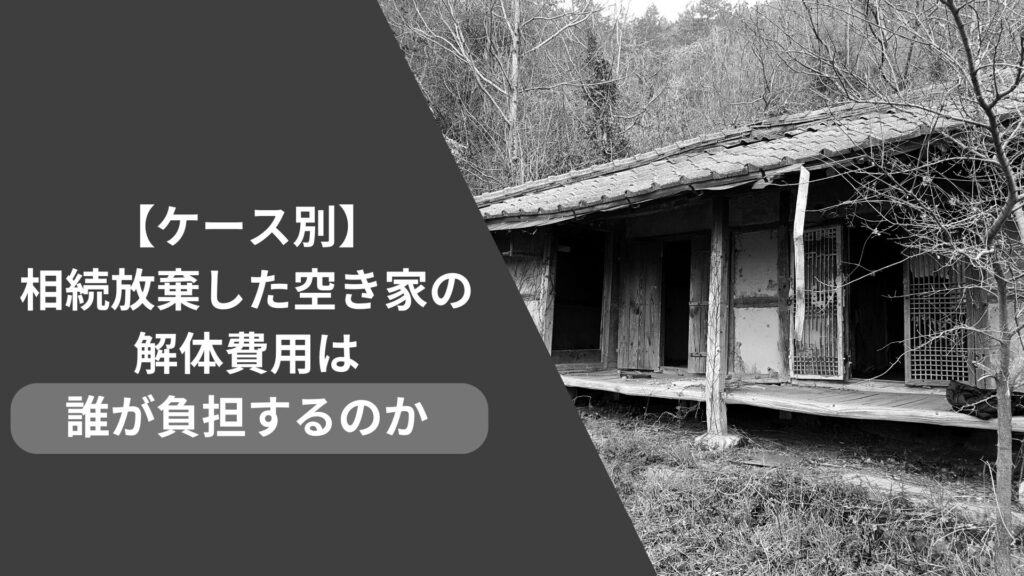
相続した空き家の解体費用は、ケースによって負担する人が異なります。他に相続人がいる場合、全員が放棄した場合、清算人がまだ決まっていない場合など、状況によって責任の所在が変わるのです。ここでは代表的な3つのケースに分けて解説します。
- ケース1.相続人ありの場合
- ケース2.全員放棄の場合
- ケース3.精算人未選任の場合
ケース1.相続人ありの場合
自身が相続放棄をしても、他に相続人がいる場合はその人が家の解体費用を負担します。たとえば、相続放棄をしても兄が相続を受け入れた場合は、兄が建物の所有者となり解体にかかるお金を支払う義務を負います。
相続には「順位」があり、最初は配偶者や子どもが相続人となり、その全員が放棄した場合は、次の順位の親や兄弟へと移っていきます。相続放棄をした人は、法律上「最初から相続人ではなかった」扱いになるため、解体費用も原則として負担しません。
ただし、家を管理していたり、荷物を保管していたりする場合は、例外的に一部の責任が問われることもあります。心配な場合は専門家に相談しましょう。
ケース2.全員放棄の場合
相続人全員が相続放棄をした場合は、誰も家の所有者にならないため空き家は「相続財産法人」という形で管理されます。相続財産法人は実際に手続きをするわけではなく、家庭裁判所に申し立てを行い相続財産清算人を選んでもらう必要があります。清算人は、弁護士などの第三者が選ばれるのが一般的です。
清算人が家を売ったり壊したりといった手続きを行い、費用も相続財産の中からまかなわれます。つまり、相続放棄をしたあなた自身が解体費用を払うことはありません。
ただし、清算人が決まるまでには1~2ヶ月ほどかかるため、空き家の状態が悪くなって近隣に迷惑をかける前に、早めの行動が大切です。
ケース3.精算人未選任の場合
相続人全員が相続放棄をしたにもかかわらず、まだ相続財産清算人も選ばれていない場合には、状況によっては相続放棄をした人が一時的に家の管理責任を負います。
たとえば、あなたが亡くなった親の家に住み続けていたり、頻繁に出入りしていたりした場合は、「現に占有している状態」と見なされます。この場合、民法940条という法律により、「最低限の管理(保存)」をする義務があるとされています。
ただし、これは家を解体する義務まで含まれるかは明確ではありません。そのため、勝手に解体を進めると、後でトラブルになることもあります。
こうした曖昧な状況では、できるだけ早く家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てるか、専門家に相談して対応方針を決めるのが賢明です。
解体費用を回避・軽減する3つの方法
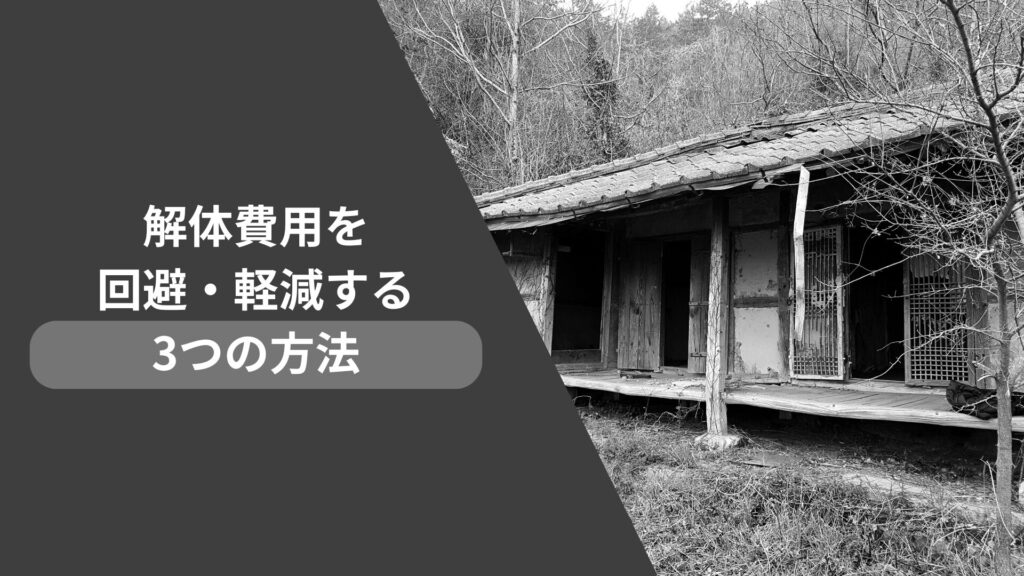
空き家の解体費用は、建物の規模や立地によって数百万円に及ぶこともありますが、工夫次第で負担を大きく減らせる可能性があります。ここでは、補助金や業者選びなど3つの方法を紹介します。
- 自治体の補助金を確認する
- 解体業者を選ぶ
- 相続放棄して費用負担しない
自治体の補助金を確認する
多くの自治体では、老朽化して危険な状態になった空き家を対象に「解体費用の補助金制度」を設けています。補助の内容は地域ごとに異なりますが、たとえば「解体費用の半額を補助(上限50万円)」といった形で支援してもらえるケースもあります。
注意点として、補助金は工事を始める前に申請して承認を受ける必要があるのが一般的です。解体後に「補助金を使いたい」と思っても、補助金を利用できないことがあります。
対象となる空き家の条件も自治体によって異なり「築30年以上」「耐震性が不足している」「人が長期間住んでいない」などの要件が設けられる場合があります。まずは空き家がある地域の役所や公式サイトで詳細を確認してみましょう。
解体業者を選ぶ
解体費用は依頼する業者によって大きく差が出ます。同じ空き家でも、業者によっては100万円近く変わることも珍しくありません。これは作業内容の内訳や人件費、廃材処分の方法などが異なるためです。
費用を抑えるには、最低でも3社以上から見積もりを取り、条件を比較することが大切です。比較する際には、以下を確認しましょう。
- 見積書に人件費や廃材処理費がきちんと含まれているか
- 追加費用が後から発生する可能性はないか
- 自治体の補助金を申請する際にサポートしてくれるか
また、解体の時期を調整するのも効果的です。繁忙期(3〜4月)を避けて依頼したり、「業者が空いている時期に工事してほしい」と交渉すれば、費用を割り引いてもらえる場合があります。
相続放棄して費用負担しない
「空き家の解体にお金をかけたくない」という理由で、相続放棄を検討する方もいます。相続放棄をすると、基本的にはその家を含むすべての財産や借金を引き継がないため、解体費用の負担を免れます。
ただし、相続放棄で解体費用を免れるには注意点があります。相続人全員が放棄した場合、相続財産清算人が家庭裁判所によって選ばれ、清算人が解体などの手続きを進めます。清算人が決まるまでの間に空き家を占有していると、管理責任を負うため解体費用を負担しなくてはいけない可能性があります。
空き家だけ放棄することはできないので、他の財産も含めてすべて確認する必要がある点も重要です。解体費用の回避を目的に安易に相続放棄を選ぶと、思わぬ損をすることもあるため、事前に専門家に相談するのがおすすめです。
空き家を解体するリスク

「相続放棄をしたのだから、もう空き家に関しては関係ない」と考えてしまう方は多いですが、実際には解体に関して思わぬ落とし穴があります。知らずに片づけや管理をしてしまい相続した扱いになるケースがあり、解体費用を負担しなくてはいけないことがあります。ここでは、空き家を解体する際に考えられる具体的なリスクを解説します。
- 放棄後でも単純承認になる可能性がある
- 費用負担がある
放棄後でも単純承認になる可能性がある
「相続放棄をしたら、関わらなくていい」と思ってしまいがちです。しかし、放棄後でも家の片づけや解体を進めてしまうと「単純承認」とみなされるおそれがあります。
単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も含めてすべて相続することです。たとえば、相続放棄をした後に遺品を勝手に処分したり、家を取り壊したりすると、「実際には相続する意思があった」と解釈される場合があります。
その結果、放棄が無効となり、空き家だけでなく借金や修繕費なども含めて全ての負担を背負うリスクがあります。良かれと思って片づけをしたことが、不利益につながってしまいます。
相続放棄を選んだ場合は、基本的に家や荷物に手を出さず、家庭裁判所で相続財産管理人が選任されるまで待つことが大切です。
費用負担がある
相続放棄をしたからといって、必ずしも解体費用の負担から完全に解放されるわけではありません。ケースによっては、費用を求められる可能性が残ります。
他の相続人がいる場合は、その人が解体費用を支払います。しかし、相続人全員が放棄した場合は「相続財産管理人」が選ばれ、解体や処分を進めます。管理人が選ばれていない段階で家を使っていたり、定期的に管理していた場合は、実質的に所有しているとみなされ、費用を負担することもあります。
また、家を放置して老朽化が進むと「特定空家」に指定され、自治体による行政代執行で強制的に解体されるケースがあります。自治体が立て替えた費用を後から請求されることもあり、数百万円にのぼるケースもあります。
注意が必要なことは、相続放棄をしても「保存義務」と呼ばれる最低限の管理責任が残る点です。雨漏りや倒壊の危険を放置したことで近隣に損害を与えれば、損害賠償を求められる可能性も否定できません。「相続放棄したら、費用も責任もなくなる」と思っていると、状況次第で解体費用や管理責任が残って負担が生じることを理解しておく必要があります。
空き家を解体しない4つのリスク

「相続放棄をしたから、もう空き家とは関係がない」と安心してしまうのは危険です。実際には、解体せずに放置した空き家が原因で、思わぬ責任や費用負担が発生するケースは少なくありません。ここでは、空き家を解体せず放置した場合にどのようなリスクがあるのか、具体的に4つの視点から解説していきます。
- 管理義務が発生する
- 特定空き家の指定
- 代執行
- 近隣トラブル
管理義務が発生する
相続放棄をしても「管理義務」という最低限の責任が残ります。管理義務とは、建物を倒壊させない・近隣に迷惑をかけないよう維持する責任のことです。たとえば屋根瓦が落ちそうな状態を放置して台風で飛んでしまった場合、その被害は元相続人に責任が及ぶ可能性があります。つまり「所有権はないけれど、安全に管理する義務はある」というのが現実です。
管理を怠ると、行政から指導や勧告を受けることもあるため、相続放棄した場合でも「完全に関係が切れるわけではない」と理解しておきましょう。
特定空き家の指定
老朽化した家をそのままにしておくと、特定空き家に指定される可能性があります。特定空き家とは、倒壊の危険や景観の悪化など、周囲に悪影響を与えていると行政に判断された空き家のことです。
指定されると、市町村から修繕や撤去の勧告を受けるほか、固定資産税の軽減措置が外れ、税額が最大6倍に跳ね上がるケースもあります。
改善命令を無視すれば、強制的に解体される行政代執行の恐れがあるため、放置しておくほど負担が大きくなると覚えておく必要があります。
代執行
特定空き家に指定されたにもかかわらず改善されない場合、行政が所有者に代わって強制的に解体する「代執行」が行われます。
解体にかかった費用は原則として所有者に請求されます。しかも行政が選定した業者が作業を行うため、一般の相場より高額になる傾向があり、数百万円単位になる事例もあります。
相続放棄をした場合でも、管理責任を果たしていなければ「一部の費用を負担せざるを得ない」と解釈されることがあるため注意が必要です。
近隣トラブル
放置された家は、害虫やネズミの温床になったり、雑草が伸びて道路や隣家に侵入したりと、周囲に迷惑をかけやすい存在です。
また、人の出入りがない家は不法侵入や放火の標的になりやすく、実際に空き家が犯罪に使われた事例も報告されています。こうした被害が近隣に及べば、住民との関係悪化や損害賠償請求につながることもあります。
「うちは相続放棄したから関係ない」と思っていても、放置が原因でトラブルが起これば無関係ではいられません。近隣との関係を守るためにも、解体や適切な管理が不可欠です。
まとめ:空き家を相続放棄するなら解体のケースも理解しておこう
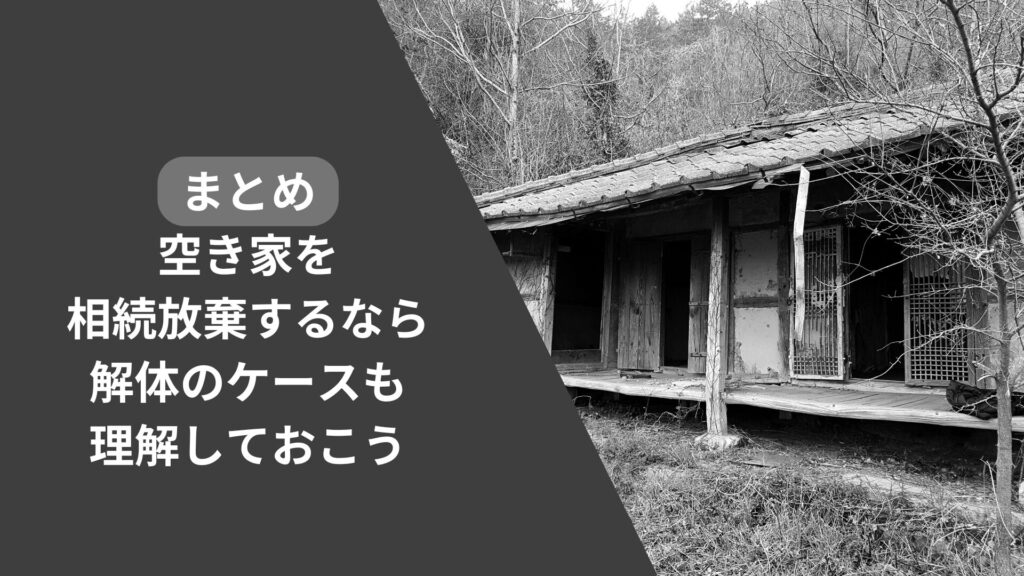
空き家を相続放棄した場合でも、解体費用や管理責任から完全に解放されるわけではありません。ケースによって「誰が負担するのか」は変わり、場合によっては放棄した相続人に責任が及ぶこともあります。
相続人がいる場合はその人が負担しますが、全員が放棄した場合は相続財産清算人が解体や処分を進めます。清算人が未選任の間に家を占有すると、管理責任を問われる可能性があります。費用を軽減するには、自治体の補助金制度を活用したり、複数の業者に見積もりを取ることが有効です。
空き家の相続では、放棄したから安心とは言えないのが現実です。重要なのは、法律や制度を正しく理解し、専門家に早めに相談して対応することです。