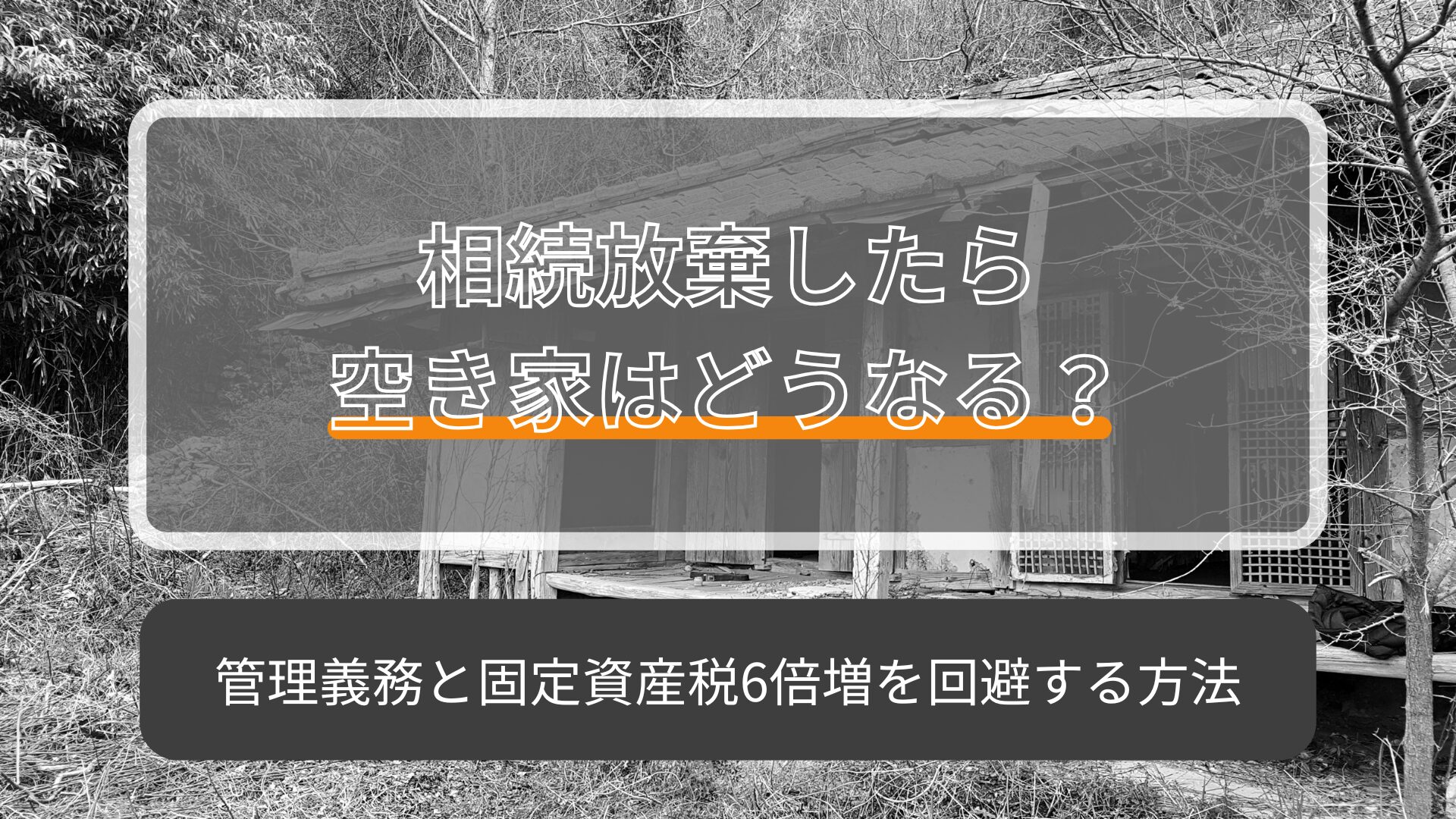相続放棄しても、空き家の問題は解決しません。実は相続放棄をしても一時的に空き家の管理義務が発生し、放置すると損害賠償や固定資産税6倍増のリスクがあります。
2023年4月の民法改正により、相続放棄後の管理責任がより明確になりました。一定の条件下では、相続放棄後も空き家を管理し続けなければならないことがあります。さらに、放置した空き家が「特定空家」や「管理不全空家」に指定されると、固定資産税の軽減措置が外れ、税負担が最大6倍に増えるリスクがあります。
- 相続放棄後の空き家管理のルール
- 管理義務や固定資産税が増えるケースとリスクを回避方法
- 空き家を手放す具体的な方法
空き家がどうなるのかを踏まえて、リスク回避の知識を一緒に確認しましょう。
相続放棄したらどうなる?→空き家の権利や義務の全てを引継がない
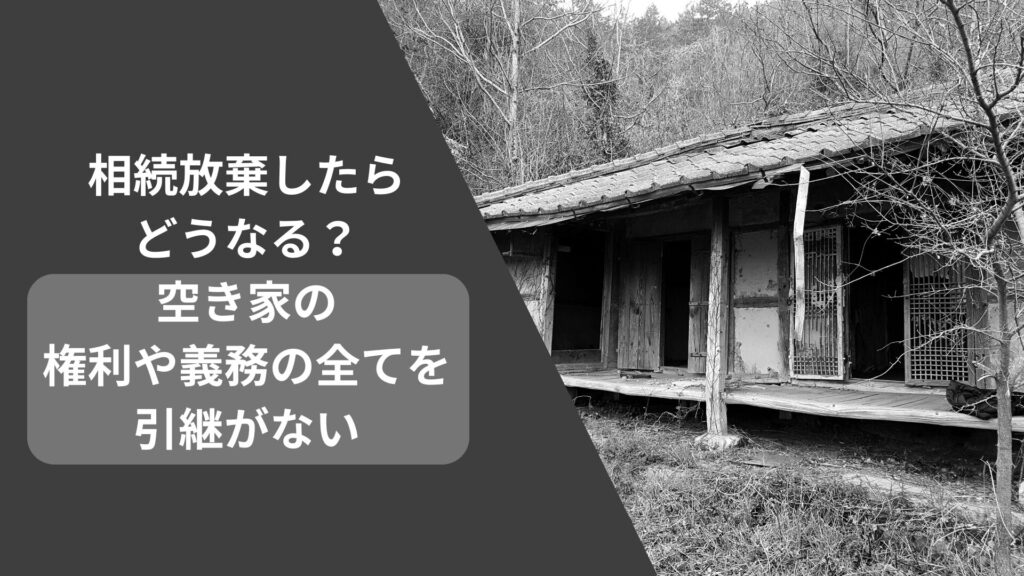
相続放棄とは、最初から相続人ではなかったとみなし、亡くなった親族の財産を一切引き継がないことです。借金や未払い金などマイナスの財産を回避できますが、思い入れのある家や預貯金など全ての遺産を相続せずに手放すことになります。
相続放棄をするためには、亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出し、手続きを完了させる必要があります。相続放棄の申述をしない場合は、相続を受け入れたものとみなされます。亡くなった人の全ての財産を引き継ぎ空き家の管理や固定資産税の支払いなどの責任が発生するため、注意が必要です。
相続放棄後の空き家管理義務とは?知っておくべき3つのポイント

相続放棄しても空き家の管理をしなくてはいけないケースがあることをご存知でしょうか。ここでは、以下の空き家の管理義務について知っておくべきポイントを解説します。
- 放棄したから管理しなくていいとはならない
- 【2023年4月法改正】相続放棄の管理責任が明確化された
- 相続財産管理人に引き渡すまで管理義務が継続する
- 適切に管理しなかった場合は損害賠償責任を負う
空き家の管理義務は相続放棄を検討する方は知っておいて損のない内容なので、読み進めて確認してみてください。
放棄したから管理しなくていいとはならない
「相続放棄をしたら、空き家を管理しなくてもいい」と考えている方は多いのではないでしょうか。しかし相続放棄をしたからといって、すぐに空き家の管理責任がなくなるわけではありません。民法では、以下のとおり定められています。
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
民法第940条
相続放棄をしたとしてもすぐに空き家の管理を免れるわけではなく、一定の責任を持って管理する義務が発生します。
【2023年4月法改正】相続放棄の管理責任が明確化された
2023年4月の民法改正によって、相続放棄後の管理義務が明確になりました。以前の民法では、相続放棄をしても空き家の管理義務が曖昧で、一部の自治体では相続放棄者に管理責任を追及するケースもありました。法改正で変わったポイントは、以下のとおりです。
- 「保存義務」と明記された
- 管理義務は「現に占有している者」に限定している
相続放棄をしたすべての人に適用されるわけではなく、空き家を占有している場合には管理義務が発生する可能性があります。管理義務を放棄するためには、相続財産管理人を選任し、空き家の管理を引き継ぐ必要があります。
相続財産管理人に引き渡すまで管理義務が継続する
民法第940条では、相続財産を現に占有している場合は次の相続人に引き渡すまで自分の財産と同じように管理しなければならないと定められています。具体的なケースは、以下のとおりです。
- 相続放棄前から空き家に住んでいた場合
- 被相続人(亡くなった親など)と同居していた場合
- 相続放棄後も鍵を持っており、事実上管理している場合
上記の場合、正式に相続財産管理人へ引き渡すまでは「保存義務」が継続するため、建物の倒壊や庭木の越境などによる近隣トラブルを防ぐために、最低限の管理が求められます。
適切に管理しなかった場合は損害賠償責任を負う
空き家の管理を適切に行わなかった結果、倒壊や火災、第三者のケガなどの損害が発生した場合、損害賠償責任を問われる可能性があります。管理義務が生じている期間は、適切な対応を取ることが重要です。
相続放棄後の管理義務を解消するためには、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てる必要があります。相続財産管理人が選任されると、その人が空き家を管理し、必要に応じて売却や処分を進めます。
空き家の相続放棄を検討する際の3つの注意点
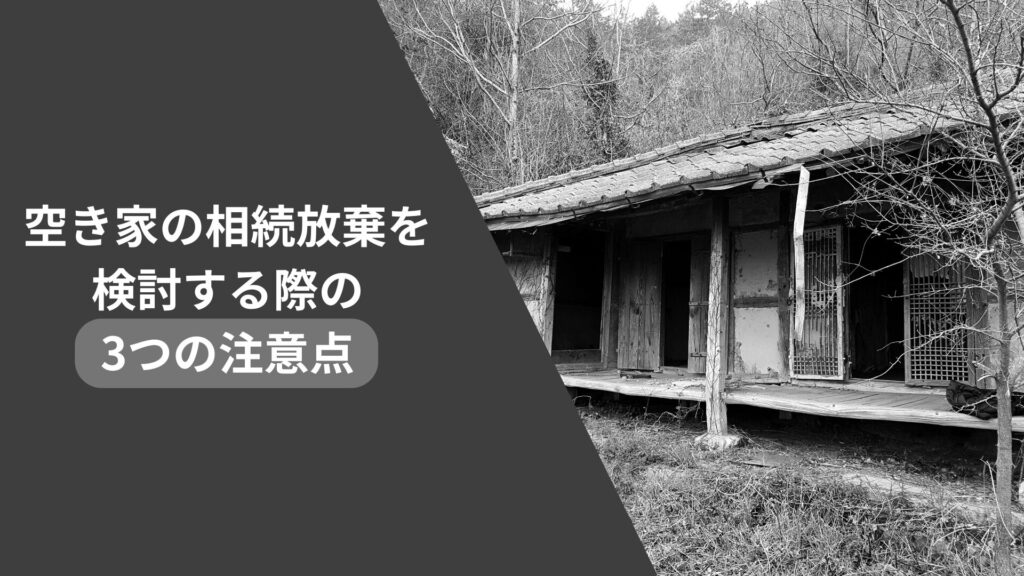
建物が空き家になってしまうことが予想される場合、相続放棄をするのかそのままの状態を維持するのがよいのか判断に迷います。
- 相続放棄には期限がある
- 空き家を放置すると固定資産税が6倍になる可能性がある
- 相続放棄は取り消しができない
ここでは、上記の相続放棄を検討する際の注意点を3つ紹介します。
相続放棄には期限がある
民法915条1項には「自分が相続人であることを知った日から3カ月以内」と定められています。この期間内で、相続するか放棄するかを判断しなくてはいけません。
相続放棄の申請期限を過ぎてしまうと自動的に相続を承認したとみなされ、借金や空き家などの財産を相続しなくてはいけません。「財産の内訳を調査するのに時間がかかる」「遠方に住んでおり手続きの準備が間に合わない」といった場合は、家庭裁判所に申立てて期限を延長できます。
相続放棄はいつでもできるものではなく、一定の期限を過ぎると自動的に相続を承認したものとみなされるため、早めに判断する必要があります。
空き家を放置すると固定資産税が6倍になる可能性がある
住宅が建っている土地は、固定資産税が最大6分の1まで軽減される「住宅用地の特例制度」が適用されます。住宅用地についての税負担軽減を目的としているので、以下の場合は固定資産税の減額が適用されないことがあります。
- 空き家を解体して更地にした場合
- 空き家が「特定空家」に指定された場合
- 空き家が「管理不全空家」に指定された場合
特定空家とは、放置されると危険な状態である使用されていない建築物で市町村長が調査等できます。管理不全空家とは、そのまま放置することで特定空家に該当する可能性がある建築物です。どちらも市町村長からの指導があっても改善されない場合、勧告を受けます。勧告を受けると、特例の対象外となり固定資産税が6倍になる可能性があります。
相続放棄は取り消しができない
相続放棄をした後で「やっぱり相続したい」と思っても、基本的に取り消すことはできません。一度手続きを進め、家庭裁判所に受理されると、原則として相続放棄を撤回することは不可能です。
ただし、相続放棄が認められた後でも以下の3つのケースに該当する場合は、例外的に取り消しが可能です。
- 未成年者などの制限行為能力者が単独で相続放棄をした場合
- 勘違いや重要な誤解があった場合
- 詐欺や強迫によって相続放棄を強いられた場合
相続放棄は、相続財産だけでなく管理義務や税負担から解放されます。検討する際は弁護士などの専門家に相談しながら、慎重に判断することが重要です。
相続放棄以外に空き家を処理する3つの方法

相続放棄だけでなく、空き家を手放す方法は他にもあります。
- 売却や買取する
- 譲渡する
- 相続土地国庫帰属制度を利用する
ここでは、上記の3つの方法を解説します。
売却や買取する
まず最初に思い付く方法は、売却や買取でしょう。売却や買取の方法は、以下の3つがあります。
- 空き家を現状のままで売却する
- 空き家を更地にしてから売却する
- 不動産会社に買取を依頼する
それぞれのメリット・デメリットをまとめました。
| 方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 現状のまま売却 | ・解体費用が不要 ・住宅用地としての固定資産税軽減措置を継続できる | ・契約不適合責任を問われる可能性がある ・古い建物は売却が難しい |
| 更地で売却 | ・買い手がつきやすい ・相続空き家の特別控除が適用できる(最高3,000万円) | ・解体費用がかかる ・固定資産税が上がる |
| 買取 | ・買い手を探す必要がない ・仲介手数料が不要 ・契約不適合責任が免責される | ・売却より価格が下がる ・立地や状態によっては買取不可のケースもある |
建物が比較的良好な状態である場合、現状での売却がおすすめです。建物が劣化している場合は、解体して更地にした方が売却しやすくなるケースがあります。不動産会社によっては「買取保証サービス」を提供している場合もあるので、早く売却したい場合は買取専門の不動産会社に相談してみましょう。
譲渡する
相手の同意さえ得られれば、親族や周辺の地権者、不動産会社などに無償で譲り渡すことが可能です。また近年では「空き家バンク」や「無償譲渡物件のマッチングサイト」など、譲受希望者を探せるサービスも増えています。
参考:国土交通省「空き家・空き地バンク総合情報ページ」
無償譲渡は、買い手がつきにくい物件でも手放せ、相続放棄の期限を過ぎてしまった場合でも選択肢になります。ただし、贈与税が発生する可能性があることには注意が必要です。無償譲渡を検討するべきケースは、以下のとおりです。
- 売却を試みたが、買い手が全く見つからない
- 固定資産税や維持費が重荷になっている
- 遠方の空き家を管理できず、早く手放したい
無償譲渡は、手間をかけずに空き家を手放せる可能性がある一方で、譲受人がすぐに見つかるとは限らない点に注意が必要です。
相続土地国庫帰属制度を利用する
売却や譲渡では処分が難しいと感じている方は「相続土地国庫帰属制度」が活用できる可能性があります。相続または遺贈によって取得した土地を、所有者の意思で国に引き渡せる制度です。この制度は、2023年4月27日に施行された「相続土地国庫帰属法」に基づく仕組みで、以下の条件を満たした土地であれば、国に返還できます。
- 相続または遺贈で取得した土地であること
- 更地であること(空き家が建っている場合は事前に解体する必要がある)
- 土壌汚染や崖地などで管理や処分に過度な費用がかからない土地であること
国庫帰属制度を利用するには、審査手数料として土地一筆当たり14,000円かかります。審査を通過するまでに数ヶ月かかることもあり、土地の状態によっては申請が通らない可能性もあります。相続土地国庫帰属制度は、所有し続けることが難しい土地の処分方法の一つですが、事前の準備や負担金の発生を考慮する必要があります。
参考:法務省「相続土地国庫帰属制度について」
まとめ:相続放棄だけが空き家の解決策ではない!
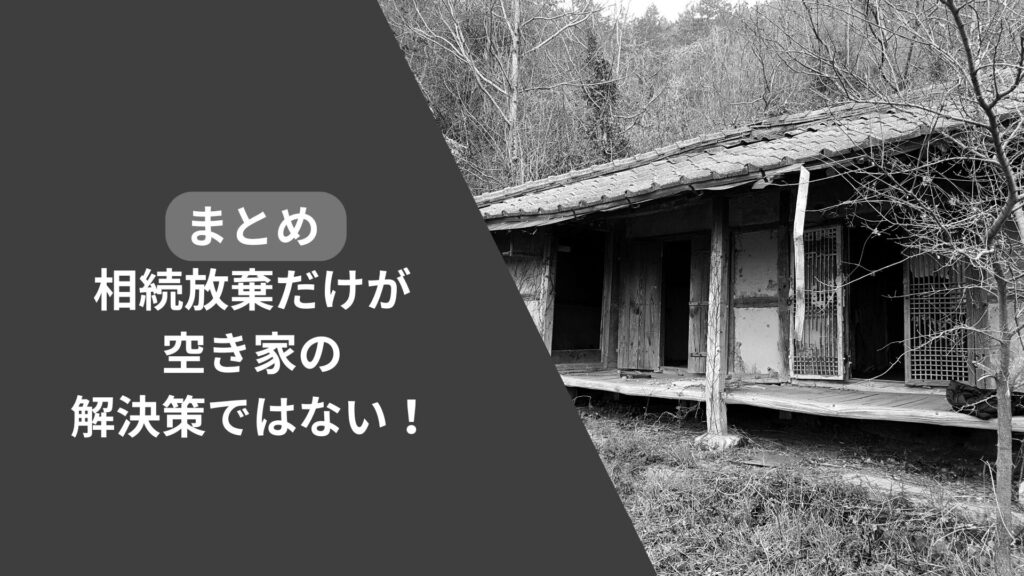
相続放棄をすると、亡くなった親族の財産を一切引き継がずに済みます。しかし、相続放棄をしても空き家の管理義務が一時的に発生する可能性があります。
2023年4月の法改正により管理が必要な範囲が明確化され、相続財産管理人に引き渡すまでは倒壊や火災などのリスクを防ぐ適切な管理をしなくてはいけません。放置すると損害賠償責任を負う可能性もあるため注意が必要です。
相続放棄には期限があり、空き家を放置すると固定資産税が6倍になる可能性があります。相続放棄は原則取り消しができないので、売却や買取、相続土地国庫帰属制度の利用も検討してみましょう。相続放棄を検討している場合は、3ヶ月の期限に注意し早めに弁護士などの専門家に相談しながら慎重に判断しましょう。