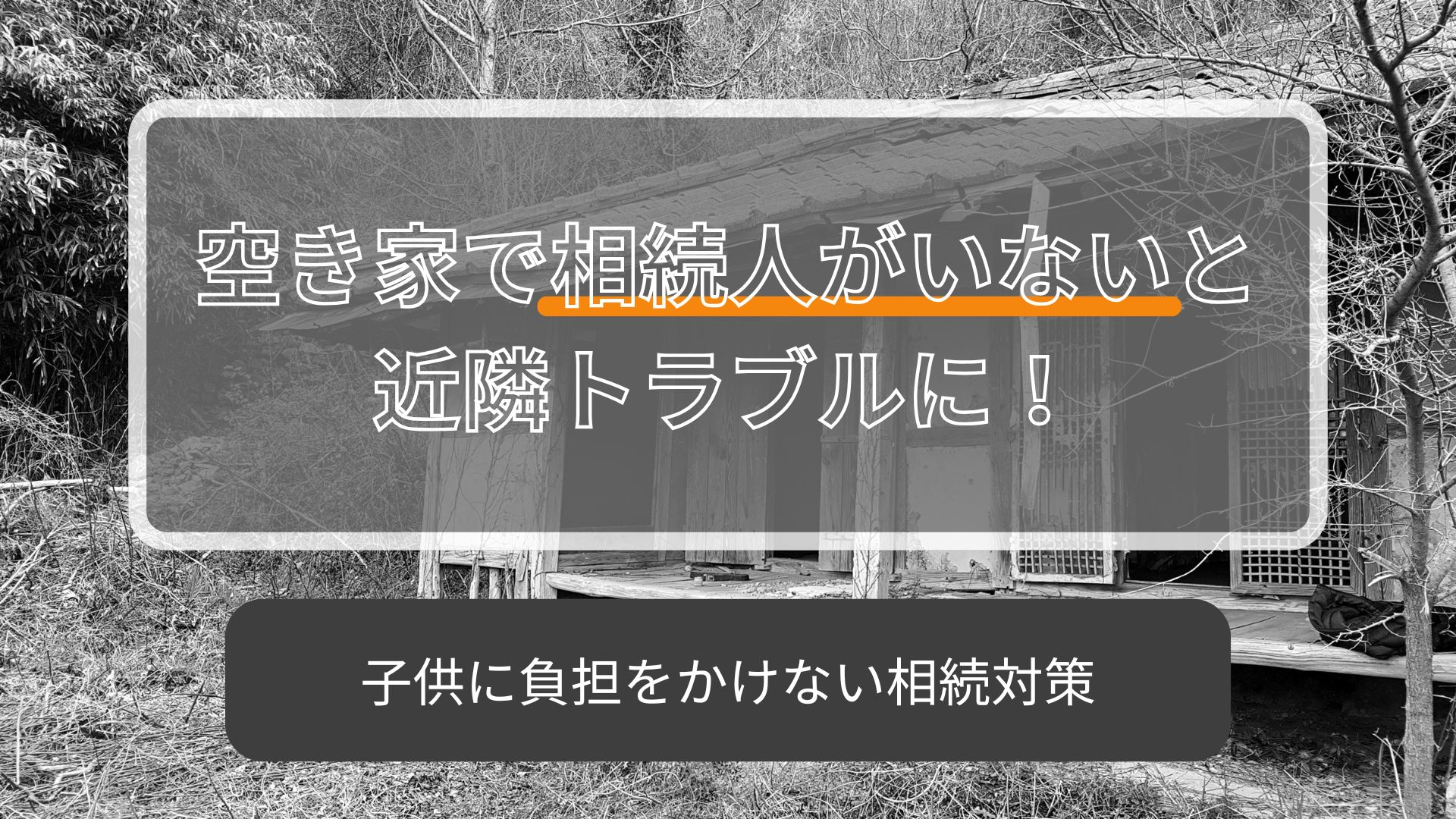今の住まいを将来誰も引き継がない場合、空き家となり近隣に迷惑をかけるのではないかと心配ではありませんか。
空き家は老朽化や防犯上の問題と、近隣とのトラブルを引き起こします。しかし事前に適切な対策を講じることで、空き家リスクを未然に防ぎ遠方に住む家族への負担を軽減できます。
- 「相続人がいない」とはどんな場合か?
- 相続人がいない空き家はどんな問題が起こるのか?
- 空き家にしない解決策は?
「何から始めたらよいのかわからない」と悩んでいる方も、不動産相続に詳しい専門家のアドバイスを活用し、安心して将来に備えましょう。
「相続人がいない」に該当する5つのケース
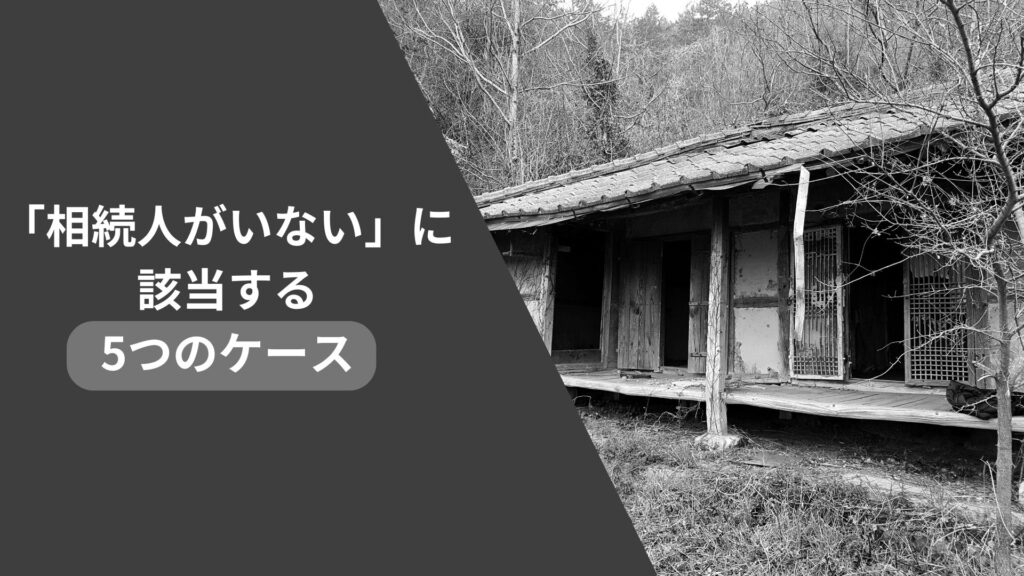
相続人がいない状態は「相続人不存在」と呼ばれ、以下の5つのケースが該当します。
- 法定相続人が1人もいない
- 相続人全員が相続放棄した
- 相続人と連絡が取れない
- 相続人が相続欠格・相続廃除になった
- 遺言書で指定された相続人がいない
ここでは、上記の5つのケースについて詳しく解説します。
法定相続人が1人もいない
法定相続人とは、民法で定められた相続の権利を持つ人のことです。法定相続人は、被相続人(亡くなった人)の財産を相続できます。法定相続人は、以下のとおりです。
| 法定相続人 | 相続する順位 |
|---|---|
| 配偶者 | 常に相続人となる |
| 子(子が亡くなっている場合は孫) | 第1順位(配偶者とともに必ず相続人となる) |
| 父母(父母が亡くなっている場合は祖父母) | 第2順位(第1順位がいない場合に相続人となる) |
| 兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥や姪) | 第3順位(第1、2順位がいない場合に相続人となる) |
上記の優先順位に従い、該当する相続人が遺産を相続します。しかし、以下を全て満たすケースでは法定相続人が存在しないため、「相続人不存在」の状態です。
- 配偶者がいない(結婚していない、または配偶者が先に亡くなっている場合)
- 子どもや孫がいない(子がいない、または子が先に亡くなっていて孫もいない場合)
- 父母や祖父母もいない(父母や祖父母がすでに亡くなっている場合)
- 兄弟姉妹がいない(兄弟姉妹が亡くなっており、甥や姪もいない場合)
被相続人が高齢の場合、法定相続人が1人もいない状態になりやすいです。ただし、行方不明で連絡が取れない状態は、「法定相続人がいない」には該当しません。
相続人全員が相続放棄した
相続放棄とは、被相続人の負債も含めた全ての財産を引き継がないことで、家庭裁判所で認めてもらいます。たとえば、被相続人が生前に多額の借金を抱えていた場合、相続人はその借金も引き継ぎます。プラスの財産よりもマイナスの財産が多ければ、相続人は代わりに返済することを避けるために相続放棄を選ぶことがあります。相続財産が不動産のみで、維持費や固定資産税が負担になる場合も相続放棄する方がいます。
被相続人との関係が希薄であり財産を相続する意欲がない場合には、相続放棄が選択されます。相続放棄をすると、その相続人は財産の相続権を完全に失います。相続放棄を選ぶ理由はさまざまですが、多くの場合、相続をすることによるデメリットが大きい場合に選択されます。
相続人と連絡が取れない
単に相続人と連絡が取れない場合は、「相続人不存在」とは認められません。しかし、連絡が取れず生死不明の状況が7年以上続いている場合、家庭裁判所の「失踪宣告」により死亡と同等の扱いができます。
まずは住民票や戸籍を追跡して、行方不明の相続人を捜索します。それでも所在が判明しない場合には、法的手続きを進めます。最終的に失踪宣告の申し立て手続きをすることを考えると、捜索の段階で弁護士に相談するとスムーズに進められます。
相続人が相続欠格・相続廃除になった
相続欠格とは、相続人が民法第891条で定められた重大な不正行為を行ったために、相続権を剥奪されることです。具体的には、次のような行為が該当します。
- 被相続人や他の相続人を殺害、または殺害を試みた場合
- 被相続人を脅迫して遺言を書かせたり変更させたりした場合
- 被相続人の遺言書を偽造、破棄、隠匿した場合
相続廃除は、被相続人の意思に基づき特定の相続人から相続権を剥奪する制度です。廃除を行うためには、被相続人が家庭裁判所に申し立てを行い、その申立てが認められる必要があります。以下のような行為が廃除の対象です。
- 被相続人に対する虐待行為
- 被相続人に対する重大な侮辱行為
- 他の相続人に対する著しい非行
相続欠格や廃除によって相続人が資格を失うと、他に法定相続人がいない場合には「相続人不存在」の状態です。
遺言書で指定された相続人がいない
遺言書で財産を受け取る人が指定されていれば、法定相続人でなくても財産を譲ることが可能です。たとえば、生計を共にしたり療養看護を行ったりした人は「特別縁故者」として遺言書に指定されることがあります。
しかし、遺言書に記載がなければ特別縁故者が財産を引き継ぐことが難しいです。家庭裁判所に認められなければ、特別縁故者としての権利がないからです。
遺言書は、被相続人の意思を確実に反映させ、財産の行方を明確にするための重要な手段です。特別縁故者がいる場合でも、遺言書を活用することで相続手続きを円滑に進められます。
相続人がいない空き家はどんなリスクがあるのか?
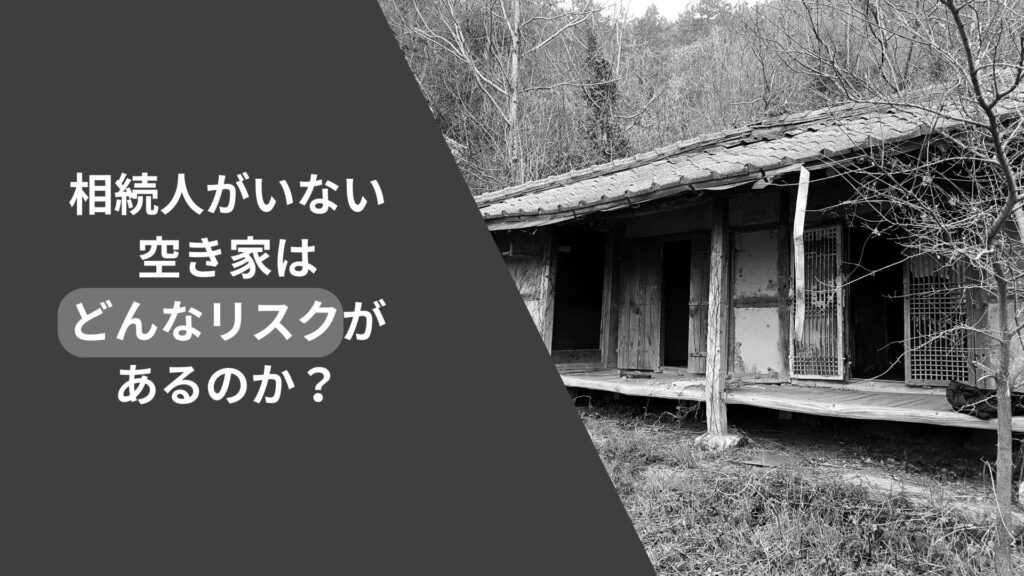
相続人がいない場合、財産に不動産があると空き家になる確率が高いでしょう。では、空き家になるとどんなリスクがあるのでしょうか。
- 老朽化による倒壊や火災の危険がある
- ゴミ屋敷となり害虫被害が発生する
- 景観が悪化する
- 犯罪の温床になる
ここでは、上記の4つのケースについて解説します。
老朽化による倒壊や火災の危険がある
空き家は定期的な換気や管理を行わないと老朽化が進み、倒壊や火災を引き起こすリスクがあります。特に1981年(昭和56年)以前に建てられた建物は、現在の耐震基準を満たしていない場合が多く、小規模な地震や台風でも倒壊の危険性が高いとされています。
また、空き家は人が住んでいないため、防火対策が不十分になりがちです。電気配線が劣化してショートによる火災の危険があるだけでなく、不法投棄や不審火にも気をつけなければいけません。
定期的な換気や掃除を行い、湿気や劣化を防ぐことが重要です。管理が難しい場合は、不動産業者に相談し空き家管理サービスの利用も検討しましょう。
ゴミ屋敷となり害虫被害が発生する
空き家が放置されると、ゴミがたまり「ゴミ屋敷」と化してしまうリスクがあります。ゴミがたまることで空き家は、以下の害虫や害獣の温床となりやすいです。
- ハエ
- ゴキブリ
- シロアリ
- ネズミ
- ハクビシン
ゴミ屋敷化した空き家は、衛生面だけでなく近隣住民にも深刻な被害を及ぼします。そのためゴミ屋敷化するのを防ぐためには、定期的な清掃と換気が重要です。ゴミ屋敷は建物の資産価値が低下するだけでなく、所有者に代わって行政が解体や清掃を行い費用請求される代執行が実施される可能性もあります。
景観が悪化する
相続人がいない空き家が放置されると、以下の理由から景観が悪化します。
- 建物の老朽化
- 庭の草木の繁茂
- 不法投棄の誘発
景観悪化は地域イメージの低下に繋がり、管理が行き届いていない場所という印象を与えてしまいます。景観が悪化した地域は、不動産価値の下落や近隣住民とのトラブルなどを引き起こします。景観悪化を防ぐためには、空き家の適切な管理、早めの売却や賃貸活用、地域や専門家との連携などが重要です。
犯罪の温床になる
人が住んでいない建物は犯罪者にとって格好の的となり、近隣住民に深刻な被害や不安をもたらします。たとえば、放火や不法占拠の心配があり、平成26年には薬物栽培するため空き家を利用していたケースがありました。特に狙われやすい空き家の特徴は、以下のとおりです。
- 施錠されていない
- フェンスや塀が破損している
- 草木が生い茂っている
- 人の出入りがなく管理されていない
空き家が犯罪に利用されると、所有者の管理責任が問われます。また、犯罪が発生することで近隣住民の安心感が損なわれ、地域全体のイメージが悪化します。
相続人がいない空き家を出さないための対処法
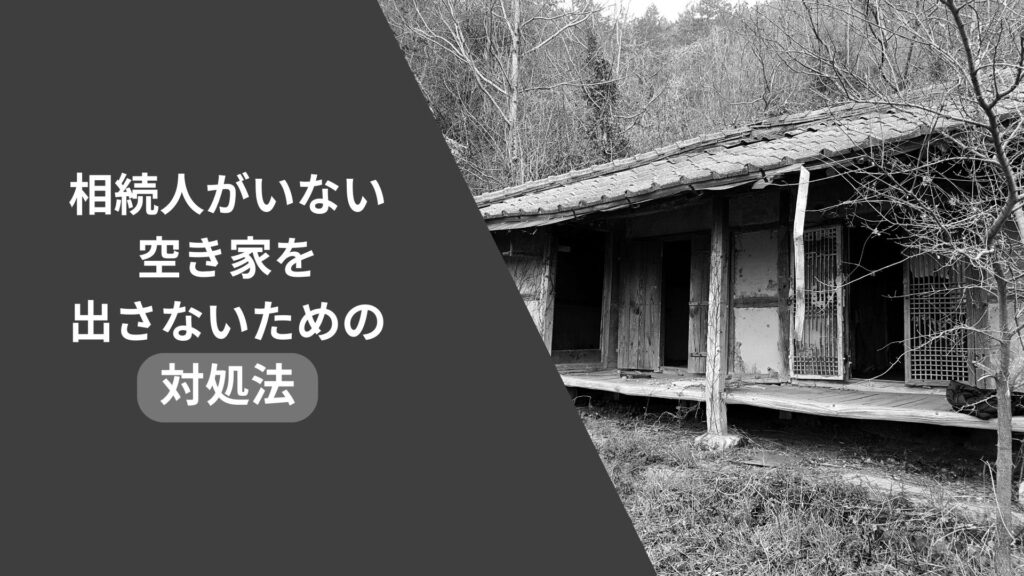
相続人がいない、でも空き家にしたくない場合はどのような対処方法があるのでしょうか。
- 遺言書を作成する
- 生前に贈与する
- 生前に売却する
ここでは、上記の3つ対処法を解説します。
遺言書を作成する
遺言書を作成すれば、財産の引継ぎ先を自分で決められます。相続人がいないと財産は最終的に国庫に帰属してしまいますが、遺言書があれば生前にお世話になった特定の個人に財産を譲ることが可能です。
たとえば、長年連れ添った内縁の配偶者や介護をしてくれた人がいても、遺言書がないと財産を確実に引継げる保証はありません。遺言の内容を実際に執行する「遺言執行者」を指定しておくと、財産の相続手続きがスムーズです。遺言執行者は特定の親族や弁護士などを指定できます。
相続人がいない状態で家を残してしまうと、空き家となり管理されずに放置される可能性が高いです。人間関係や財産状況は時間とともに変化するため、一度作成した遺言書の内容を見直して、必要に応じて書き換えを行うことが重要です。
生前に贈与する
生前贈与は、文字通り生きている間に自分の財産を他の人に譲ることです。遺言書と異なり、生前に贈与することで財産を確実に渡せます。
生前に贈与することで、相続後に空き家が発生するのを防げます。相続発生時に財産が残らないので、相続税の負担が軽減されます。注意点として、贈与税の負担が発生する可能性があるので、持分を少しずつ渡す場合は1年間に110万円を超えないように計画的に進めることが重要です。
生前に売却する
「このままだと空き家になる」と分かっているなら、生前に売却を検討することが最善の対策です。生前に売却するメリットは、以下のとおりです。
- 早く売却するほど高値で売れる
- 維持管理費を削減できる
- 売却した資金を老後の生活費として活用できる
土地や建物は時間の経過とともに資産価値が下がります。築年数が浅いうちに売れば高値がつきやすく、修繕費用をかけずに売却できます。また、売却資金を介護施設や高齢者向け住宅への引っ越し費用に充てられます。相続人がいない場合、資産の使い道を自由に決められるので、自分の意志に沿った形で活用できます。
売却のタイミングが遅れると、建物の価値がさらに下がり、売却価格が低くなってしまいます。「今すぐ住む予定がない」「相続人がいない」と思った時点で売却を検討しましょう。
空き家にしないために相談できる専門家
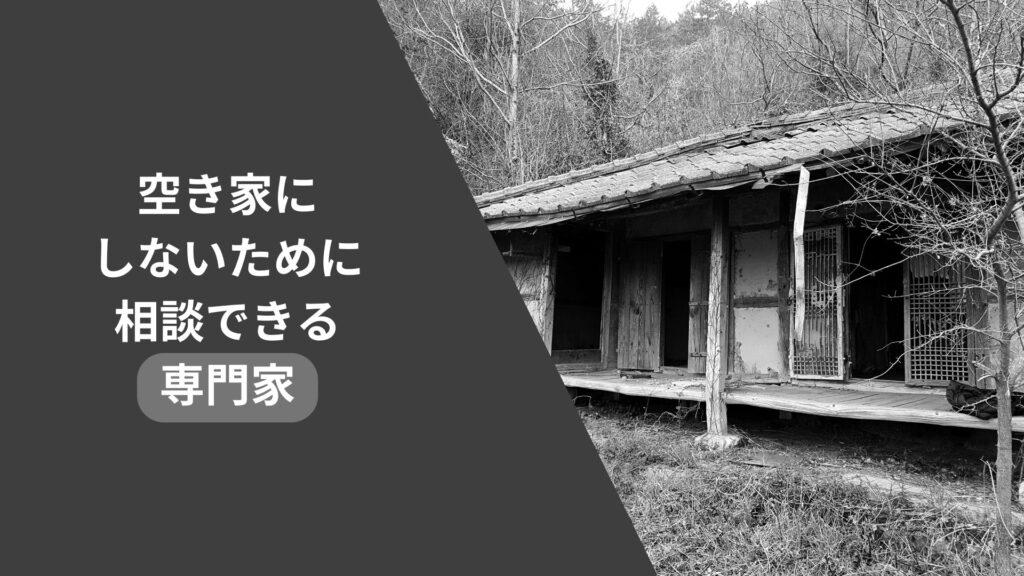
相続人がいないために家を放置すると、空き家リスクが高まり近隣トラブルを引き起こします。適切な対策を講じるためには、専門家の力を借りることが重要です。以下に、相談できる専門家とその役割をまとめました。
| 専門家 | 役割 |
| 弁護士 | ・相続問題全般の法的アドバイス ・複雑な相続関係でも対応可能 |
| 司法書士 | ・相続登記の書類作成や代理申請 ・遺産分割協議書の作成 |
| 税理士 | ・相続税の申告 ・節税対策などの税務相談 |
| 行政書士 | ・遺言書の作成支援 ・相続手続き全般をサポート |
| 不動産会社 | ・空き家の売却や賃貸、管理についての相談 ・空き家の査定 |
上記の専門家と連携し適切な対策を講じることで、空き家問題を未然に防ぎ、後のトラブルを未然に防げます。
まとめ:相続人がいない場合は専門家に相談を!
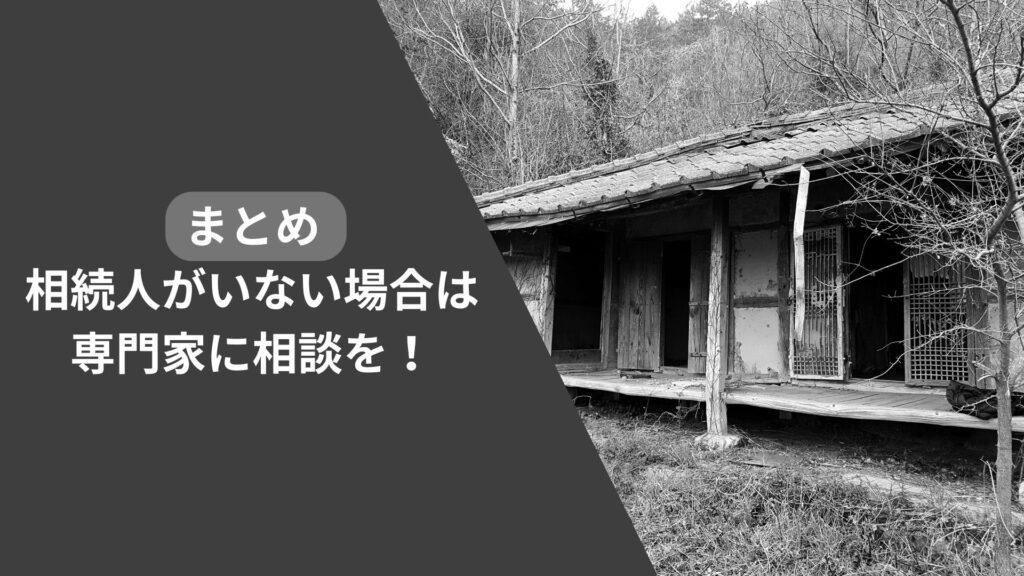
相続人がいない状態では、相続財産の住宅が空き家になるリスクが高いです。空き家を放置すると老朽化だけでなく、害虫被害や犯罪の温床などさまざまなリスクが生じ、近隣住民とのトラブルにつながります。
空き家リスクを避けるためには、遺言書を作成したり生前に売却したりするなど、対策が必要です。不動産会社や弁護士など専門家に相談することで、適切な対応でリスクを最小限に抑えられます。相続人がいない場合には特に対応が求められる状況と言えるので、専門家の支援を活用し空き家問題を未然に防ぎましょう。