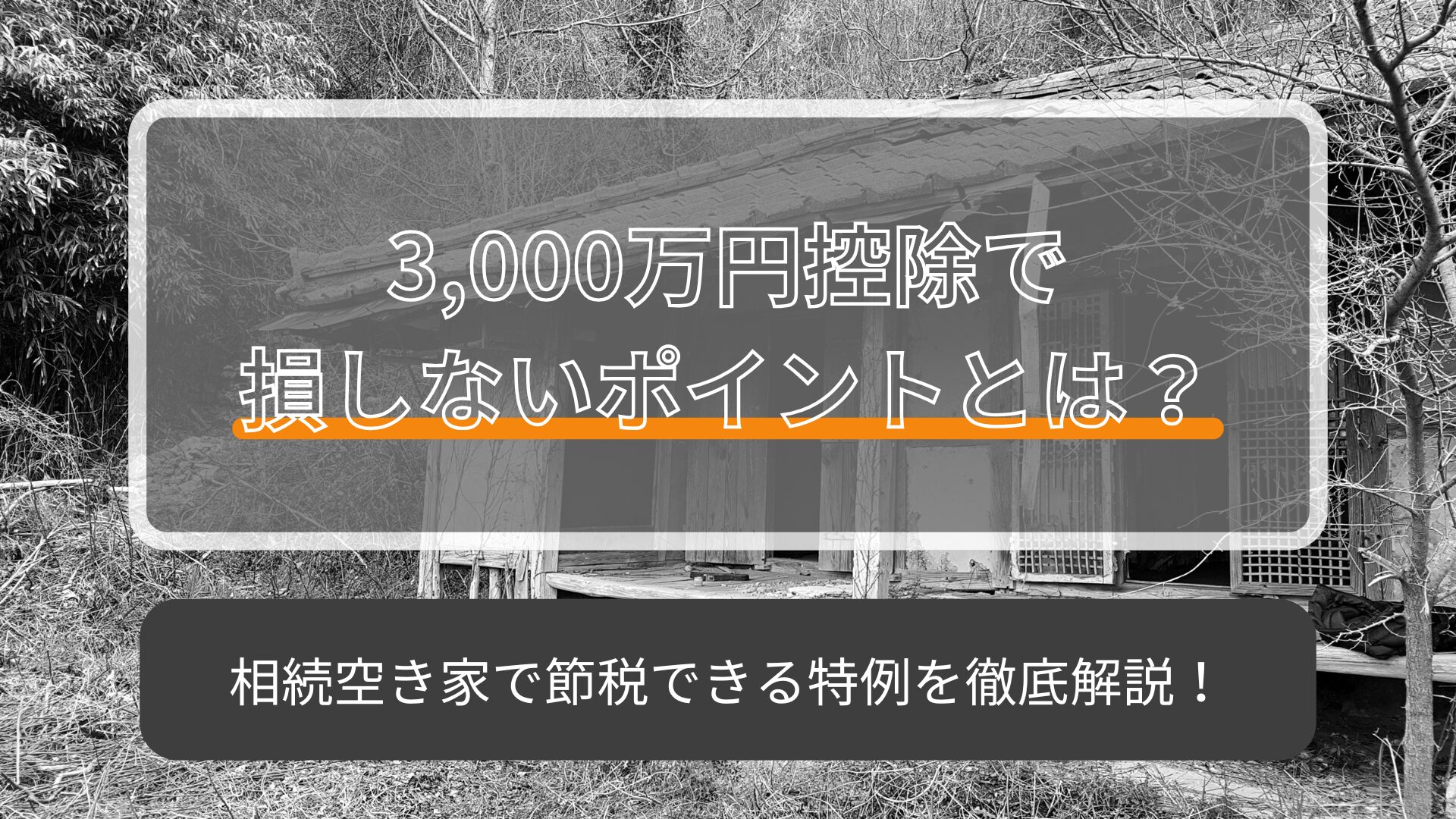相続した空き家の売却を検討するなら、知っておいてほしい特別控除があります。「3,000万円特別控除(空き家特例)」を活用すれば、譲渡所得から最大3,000万円を控除でき、税負担の軽減が期待できます。
ただし控除するには適用要件が多く、知らずに進めると控除が受けられない事態になりかねません。「適用できない売却先がある」「どの特例が併用できるのか」など、細かい情報まで知っておくと売却をスムーズに進められます。
- 「3,000万円特別控除(空き家特例)」の適用に必要な要件が理解できる
- 特例を受けるために必要な書類や手続きの流れを把握できる
- 生前贈与や他の特例との併用ルールや注意点を知り、損をしない判断ができる
この記事では、空き家特例の要件から申告手続きや注意点までわかりやすく解説します。相続した実家を損することなく売却したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
相続した空き家を売却して譲渡所得から最高3,000万円控除できる特例
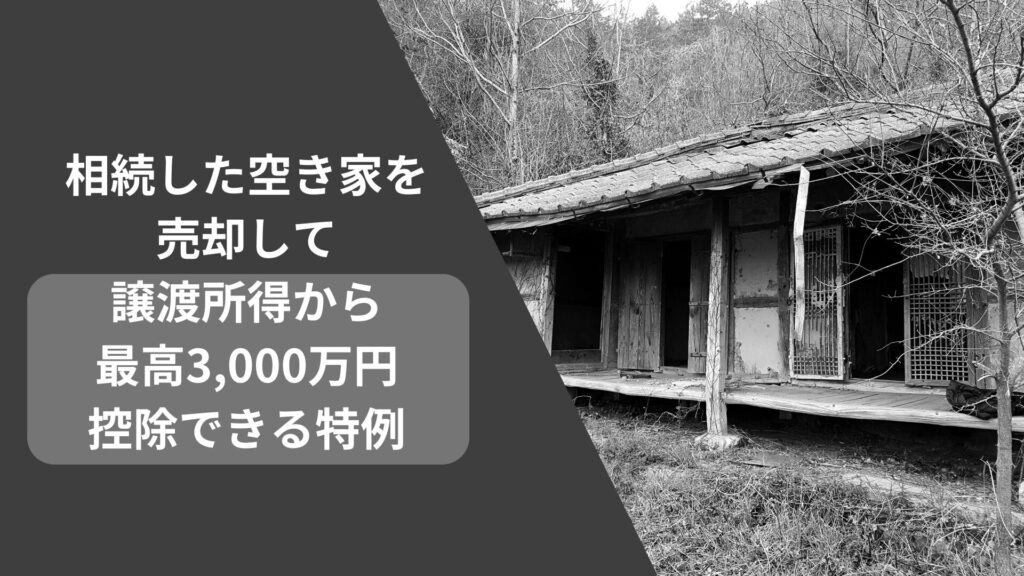
相続した空き家を売却する際「空き家特例」を活用すると、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。親などの被相続人(亡くなった方)が住んでいた家を相続し、一定の条件を満たして売却した場合に適用される特別控除の制度です。
「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」または「空き家特例」とも呼ばれます。被相続人の居住用財産であった家屋やその敷地を相続した相続人が、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売却した譲渡所得が対象です。適用するためには一定の要件を満たす必要があるため、売却前に条件を確認しスムーズに申請できるよう準備しておくことが大切です。
3,000万円特別控除の6つの適用要件
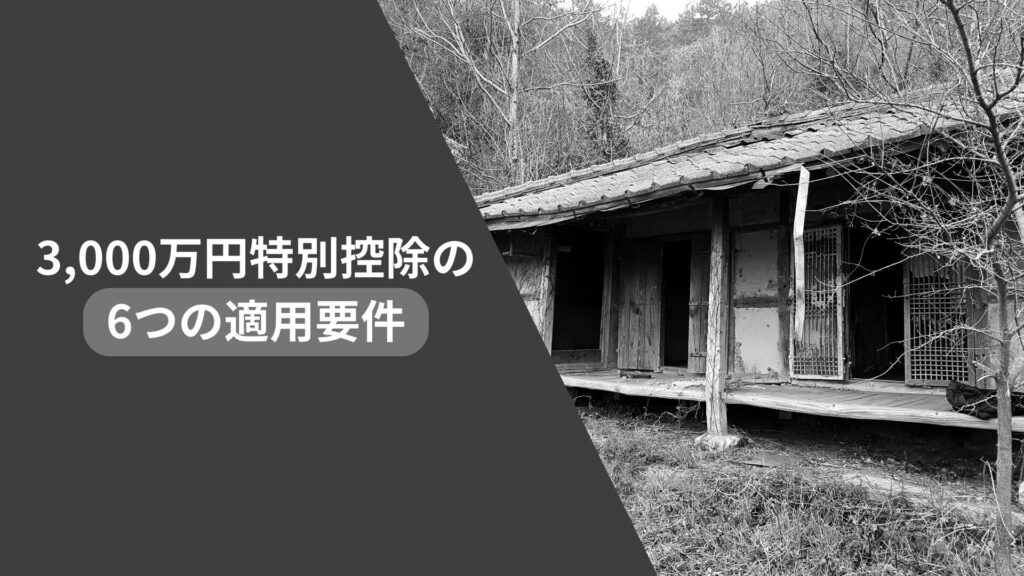
特例を適用するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 相続または遺贈であること
- 居住用家屋を売却していること
- 相続開始から3年を経過した年の12月31日までに売ること
- 売却代金が1億円以下であること
- 他の特例の適用を受けていないこと
- 「特別の関係がある人」に対して売ったものでないこと
それぞれの要件について詳しく解説します。
相続または遺贈であること
特例を利用するためには、相続または遺贈(死因贈与を含む)により空き家を取得した相続人であることが条件です。亡くなった方(被相続人)の居住していた家やその敷地を、法定相続または遺言による遺贈で受け継いだ場合に適用されます。
たとえば親が住んでいた家を子どもが相続し、その後売却するケースでは特例の対象になります。ただし、生前贈与を受けた場合は対象外となるため注意が必要です。
居住用家屋を売却していること
売却する家は、被相続人の居住用家屋であることが条件です。単なる空き地の売却や、事業用や賃貸用として利用していた場合は適用されません。対象となる家屋とは、以下の3つの要件を満たすものです。
- 昭和56年5月31日以前に建築されている
- 区分所有建物(マンションなど)ではない
- 相続開始時点で、亡くなった方以外に住んでいた人がいない
一定の耐震基準を満たす一戸建ての空き家が対象であり、マンションは適用されません。家族が一緒に住んでいた場合は、対象外です。平成31年4月1日以降の譲渡については、被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所していた場合でも、一定の条件を満たせば特例が適用されるようになりました。
相続開始から3年を経過した年の12月31日までに売ること
特別控除を適用するには、相続の開始があった日(被相続人が亡くなった日)から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却しなくてはいけません。たとえば、2023年1月15日に相続が発生した場合、2026年12月31日までに売却しなければいけません。この期限を過ぎると特例の適用を受けられなくなるため、売却のタイミングには注意が必要です。
空き家の売却には時間がかかることもあるため、相続が発生したら早めに売却の計画を立てることが大切です。期限ギリギリで焦ることがないよう、手続きのスケジュールを不動産会社と確認しながら進めましょう。
売却代金が1億円以下であること
売却代金は1億円以下であることが条件です。1億円かどうかの判定は相続人ごとではなく、分割した部分や他の相続人の部分も含めた全体の売却代金の合計で行われます。
たとえば、相続した家屋や土地を複数回に分けて1回目は5,000万円で売却し、2回目は6,000万円で売却した場合、合計額は1億1,000万円となり超えた分は追加で修正申告と納税が必要です。他の相続人が同じ不動産を売却した場合も、すべて合算して1億円を超えていないかをチェックする必要があります。
他の特例の適用を受けていないこと
すでに他の特例を受けている場合は、3,000万円控除の適用を受けられません。
たとえば、「相続財産を譲渡した際に取得費加算の特例」を適用している場合、その財産に関しては3,000万円控除を適用できません。この特例は、相続または遺贈によって取得した土地や建物を譲渡した際に、相続税額の一部を譲渡資産の取得費に加算できるというものです。
また、この特例を適用するのは、初めてでなければいけません。したがって、同一の被相続人から相続等で取得した家屋や敷地について、この特例を受けていないことも要件となります。相続人1人につき、1回しか適用できないと覚えておきましょう。
「特別の関係がある人」に対して売ったものでないこと
売却先が「特別の関係がある人」でないと、3,000万円特別控除を受けられません。ここでいう「特別の関係がある人」とは、以下の関係者です。
- 親子・夫婦などの法定親族
- 生計を一にする親族(同じ家計で暮らしている兄弟姉妹など)
- 売却後にその家で一緒に住む予定の親族
- 内縁関係にある人(法律上の婚姻関係がないが事実上の夫婦関係にある人)
- 売却者と密接な関係にある法人(家族経営の会社など)
関係者を除外している理由は、形式上の売却を装って税負担を軽くする不正を防ぐためです。そのため、売却の相手が第三者であることが前提となっています。
仮に、売却先が「特別の関係がある人」に該当する場合、特例は使えず、譲渡所得全額に対して課税されます。売却後に同居予定の親族がいる場合は、事前に関係性が特例の対象外に該当するかを確認しておきましょう。
特別控除を受けるための手続き

相続した空き家を売却して「3,000万円の特別控除」を受けるには、確定申告の手続きが必須です。申告をしなければ、せっかくの特例も使えません。
- 必要書類一覧
- 手続きの流れ
ここでは、準備すべき書類の一覧と、手続きの具体的な流れについてわかりやすく解説します。
必要書類一覧
相続空き家の3,000万円特別控除を受けるには、確定申告での手続きが必要です。自動的に適用されるものではないので、以下の書類をそろえて申告しましょう。
| 書類名称 | 取得先 |
| 確定申告書 | 税務署または国税庁HP |
| 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書[土地・建物用]) | 税務署または国税庁HP |
| 売却時の売買契約書(写し) | 不動産会社(売却時) |
| 売却時の諸費用の領収書(写し) | 不動産会社等(売却時) |
| 登記事項証明書 | 法務局 |
| 被相続人居住用家屋等確認書(空き家の場合) | 市区町村 |
| 戸籍の附票(写し)(被相続人の居住用の場合) | 市区町村 |
| 耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し(空き家の場合) | 建築士や指定検査機関 |
特例を受けるためには、期限内に確定申告をしなくてはいけません。書類によっては取得に数日~1週間以上かかることがあります。売却が終わったら早めに準備を始めるのがおすすめです。
手続きの流れ
特例の適用を受けるまでの流れは、以下のとおりです。
- 譲渡契約
- 特例の適用要件を確認する
- 必要書類を取得する
- 申告書を作成する
- 確定申告
- 納税
譲渡所得が発生する場合は、申告後に納税しなくてはいけません。
特例を適用するための4つの注意点
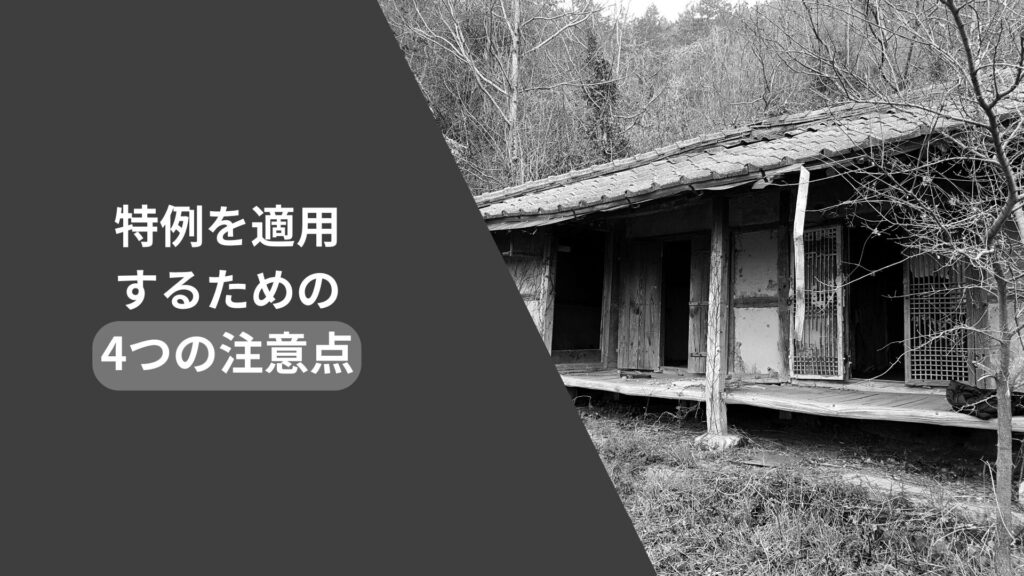
特例を使うには、単に条件を満たしているだけでは足りません。ここでは、特例を確実に活用するために押さえておきたい注意点をわかりやすく整理しました。
- 確定申告が必要
- 生前贈与の場合は適用外
- 併用できる特例と併用できない特例がある
- 取り壊すと適用されない可能性がある
申告漏れや制度の誤解で損をしないよう、ぜひ確認しておきましょう。
確定申告が必要
相続した空き家を売却し、3,000万円特別控除を適用するには確定申告が必要です。売却によって得られた譲渡益に税金がかからなかった場合、つまり納税額が「0円」になるケースでも変わりません。自動的に控除されることはなく、自分で申告しないと適用されない点に注意しましょう。
確定申告は、書類を揃えて申告期間内に正確に提出することが必要です。特例を使えば大きな節税が期待できますが、書類不備や申告漏れがあると、控除が受けられず損をする可能性があります。申告ミスがあっても後に訂正ができないケースもあるため、注意が必要です。
生前贈与の場合は適用外
3,000万円特別控除の特例は、相続または遺贈によって取得した空き家に限って適用される制度です。したがって、亡くなった方から生前に家屋や土地の贈与を受けていると、特例の対象外です。
たとえば親から実家を生前贈与で譲り受けていた場合、贈与後も親が住み続けていたとしても、相続による取得ではないため、3,000万円の特別控除は適用されません。相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた場合も同様です。親と共有になっていた場合は、相続で取得した持ち分に対してのみ適用されます。
将来の相続を見越して贈与しておく方が有利と思いがちですが、生前贈与を選ぶと特例を使えなくなるリスクがあることは理解しておきましょう。
併用できる特例と併用できない特例がある
「3,000万円特別控除」は節税効果がある制度ですが、一部で併用できない特例があります。併用できるかどうかの一例は、以下のとおりです。
| 特例 | 内容 | 適用可否 |
| 小規模宅地等の特例 | 相続税の評価額を減額できる | 併用可 |
| 住宅ローン控除 | 住宅ローンの残高に応じて所得税や住民税が控除できる | 併用可 |
| 居住用財産の3,000万円控除 | マイホームを売却したときに譲渡所得を控除できる | 併用可(同一年内) |
| 相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例 | 譲渡した相続財産の取得費に相続税額を加算できる | 併用不可 |
「知らなかった」で損をしないよう、早めの情報収集と準備が大切です。併用の可否は特例制度を理解する必要がありますが、具体的に計算したい場合は税理士に相談しましょう。
取り壊すと適用されない可能性がある
2024年の法改正により、売却後に空き家を取り壊した場合でも特例の対象となることが明確化されました。これまでは売却前に解体する必要がありましたが、買主が解体・耐震改修しても空き家の譲渡所得の特別控除を利用できます。
ただし、適用期間が延長されたにすぎません。注意すべきは、2024年1月1日~2029年12月31日までに、対象の空き家を売却しなければ制度を利用できないことです。
しかし、解体後の方が土地として販売しやすく買主が自由に活用できる点で、売却しやすいのも事実です。節税だけでなくスムーズな売却やトラブル防止も考慮すると、早めに建物を解体して準備を進める方が現実的です。
まとめ:相続した空き家を売却する際は特例の要件を把握しておく
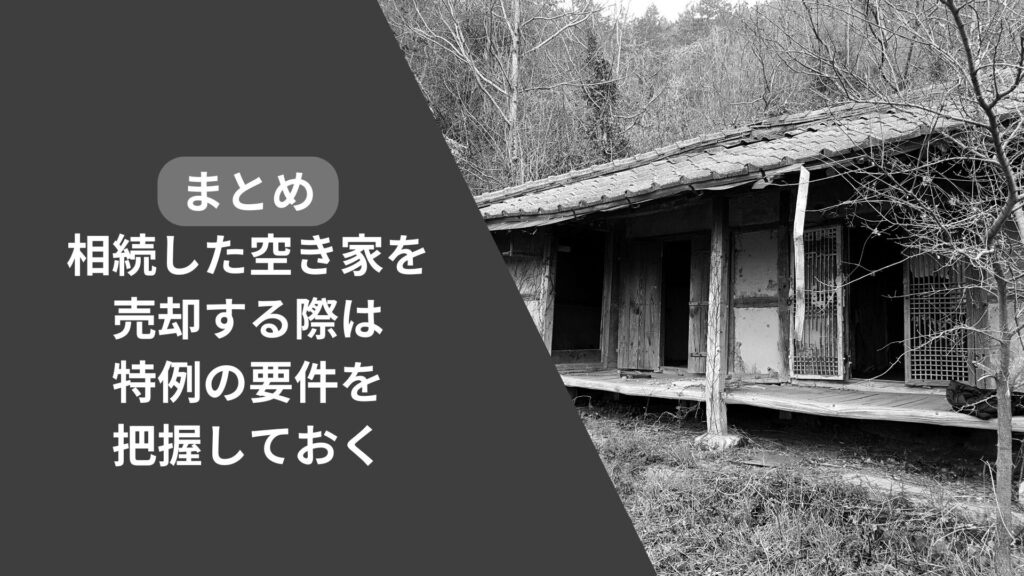
相続した空き家を売却する場合、「3,000万円特別控除(空き家特例)」を活用することで、大きな節税効果が期待できます。ただし、この特例を受けるには相続による取得であることや売却時期、売却先の条件など、複数の要件を満たす必要があります。
注意すべきは、確定申告による手続きが必須であり、必要書類の準備や申告内容に不備があると控除を受けられない可能性があることです。生前贈与された物件は対象外である点や、他の特例との併用可否にも注意が必要です。
空き家を売却する前に、制度の仕組みや注意点をしっかり理解し、計画的に進めるましょう。少しでも不安がある場合は、早めに相続の専門家や税理士へ相談することをおすすめします。