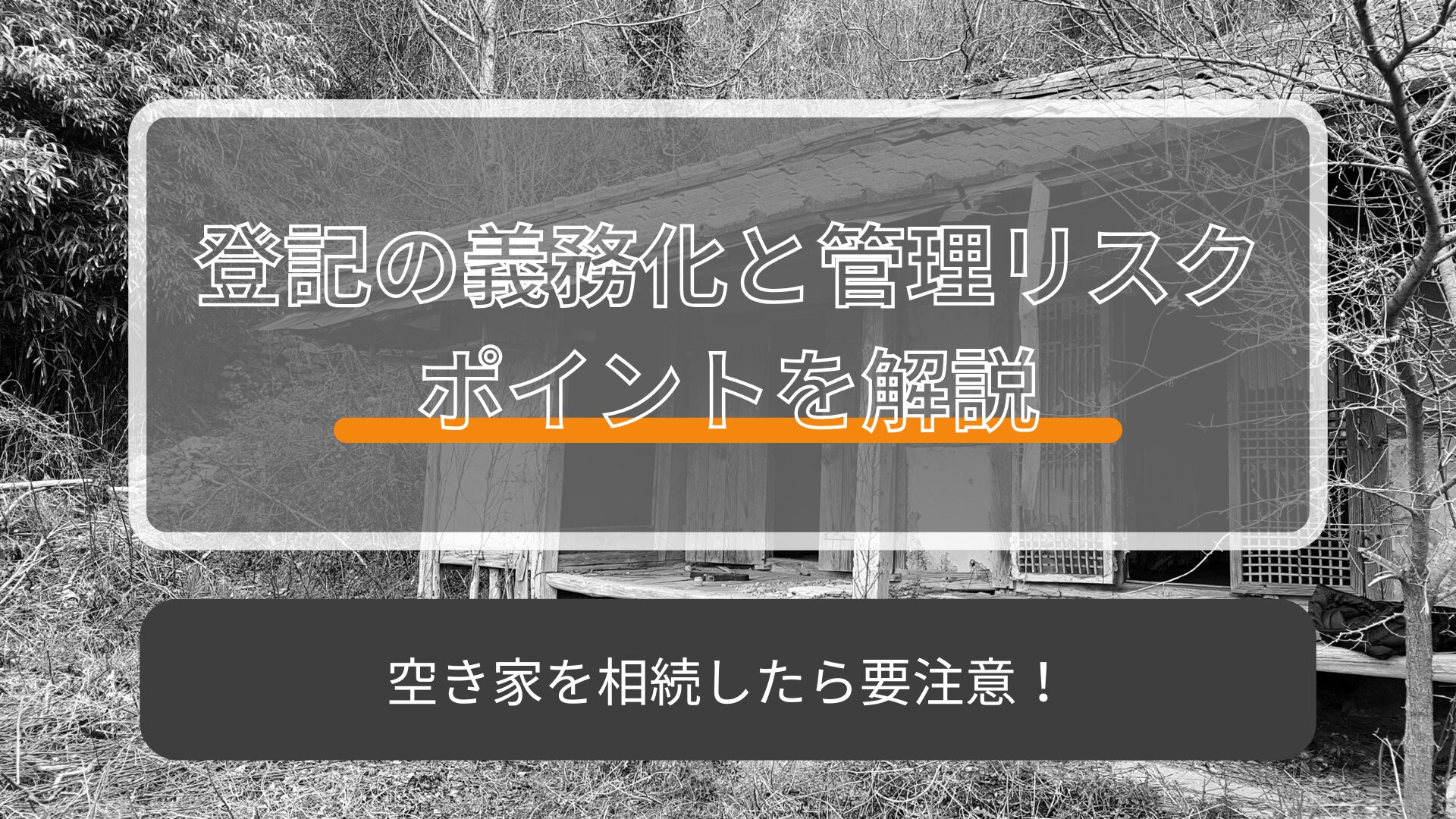空き家を相続したものの「何から始めればいいのかわからない」「このまま放置しても大丈夫かな」と不安に感じていませんか。2024年4月から相続登記が義務化されただけでなく、放っておくと思わぬ費用負担が発生するリスクがあります。
たとえば名義を変更しないまま相続不動産を放置して特定空き家に指定されると、固定資産税が最大6倍になったり、代執行により多額の解体費用を請求されたりする可能性があります。
- 相続登記の義務化とその対応方法
- 空き家を相続した際の管理責任と費用リスク
- 空き家を活用・処分するための具体的な選択肢
この記事では、相続登記の基礎知識と、空き家を管理するための具体的な選択肢をわかりやすく解説します。何から始めればいいのかが明確になり、所有者の負担を最小限に抑えるヒントが得られます。
相続登記は2024年4月から義務化された内容
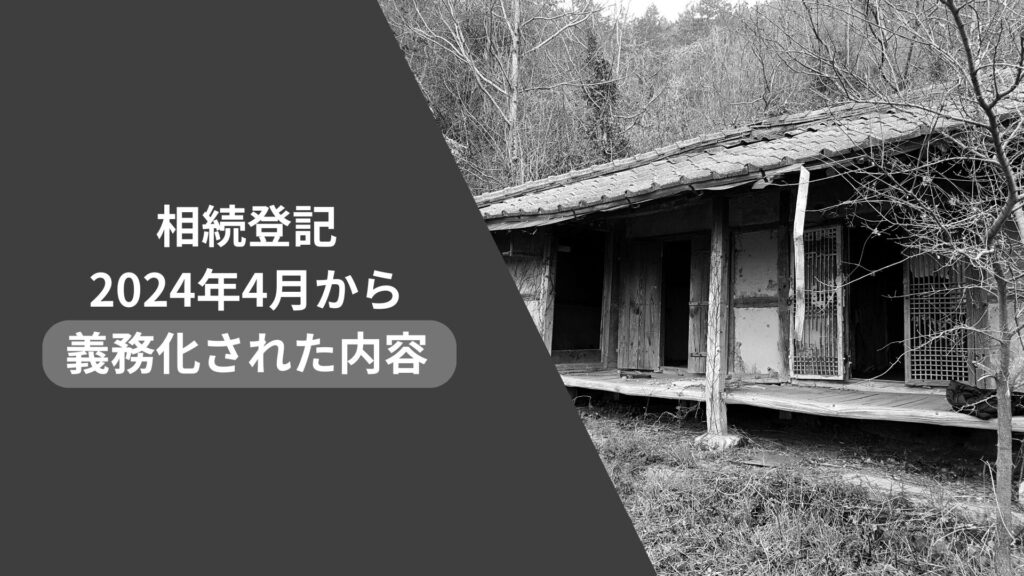
相続登記の義務化によって、名義変更を怠ると過料が科されるリスクがあります。ここでは何をいつまでにすべきなのかなど、知らなかったでは済まされない重要なポイントを解説します。
- 相続登記の申請が義務化された
- 正当な理由がないとペナルティの対象になる
- 義務化の理由は所有者不明土地の問題を解決するため
相続登記の申請が義務化された
2024年4月1日から、不動産を相続した際の相続登記が法律で義務になりました。相続登記は、亡くなった方(被相続人)が所有していた土地や建物の名義を、相続人に変更する手続きのことです。たとえば、父親が所有していた実家を長男が相続する場合、不動産の登記名義を父から長男に変更します。
義務化により、相続人は不動産を相続したと知った日から3年以内に登記を申請しなければいけません。2024年4月以降に発生した相続だけでなく、過去に相続したまま登記していない不動産にも適用されます。その場合は、2027年3月末までに手続きを済ませなければいけません。
正当な理由がないとペナルティの対象になる
法律で義務付けられた相続登記は、正当な理由がなく怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
過料とは,行政上の秩序の維持のために違反者に制裁として金銭的負担を課すものです。刑事事件の罰金とは異なり,過料に科せられた事実は,前科にはなりません。(裁判所ホームページより引用)
「正当な理由」と認められるケースには、以下のような状況があります。
- 相続人が非常に多く、全員の戸籍や同意を集めるのに時間がかかる
- 相続人の一人が重い病気で、手続きに関われない
- 遺言書の有効性について争いがある
- 相続人の生活が困窮していて、すぐに手続きができない
該当すれかの判断は登記官の裁量によるため、必ず免除されるとは限りません。
義務化の理由は所有者不明土地の問題を解決するため
これまで、相続によって不動産を引き継いでも登記の申請は任意でした。そのため、相続登記がされないまま年月が経ち、誰が本当の所有者なのか分からない土地や建物が全国に広がっています。
所有者不明の不動産は、売却や活用ができないだけでなく、空き家や空き地として放置され、ゴミの不法投棄や近隣トラブルの原因です。道路や防災施設などの公共工事が計画通りに進まないこともあり、社会全体に大きな影響を及ぼしています。
主な原因のひとつが「相続登記がされていないこと」です。登記されていなければ、法務局の記録にも新しい所有者が反映されません。こうした事態を解消し、不動産の管理責任を明確にするために、相続登記は義務化されました。
不動産の相続人を決める遺産分割協議の流れ
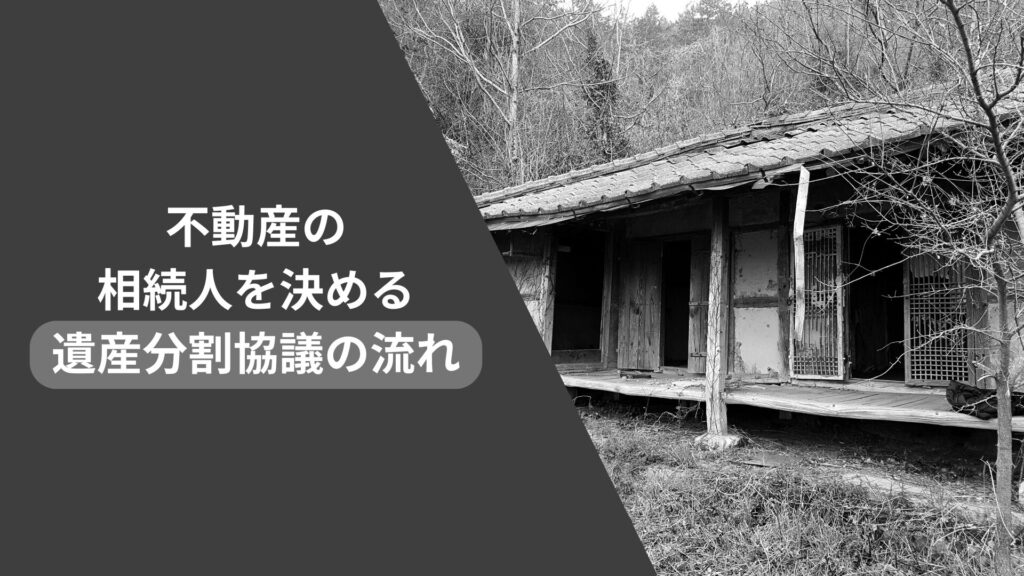
空き家を相続すると決まったら、相続人同士で話し合って不動産の分け方を決める「遺産分割協議」が必要です。ここでは、相続人の確定から協議書の作成まで、遺産分割協議の手順を解説します。
- 誰が相続人か?戸籍の内容を確認する
- 相続財産は?固定資産税の納税通知書で不動産を確認する
- 誰が何を相続する?相続人全員で遺産分割協議を行う
誰が相続人か?戸籍の内容を確認する
空き家を相続する場合、最初に相続人を確定します。相続人を確定しないと、遺産分割協議ができません。遺産分割協議は、相続人全員で「誰がどの財産を相続するか」を決める話し合いです。すべての法定相続人が参加する必要があるため、1人でも抜けてしまうと協議が無効になるおそれがあります。
相続人は、被相続人(亡くなった方)の出生から亡くなった日までの戸籍を確認します。全ての戸籍を取得することで、たとえば「認知していた子どもがいた」「再婚歴があり前の配偶者との子がいた」といった情報も明らかになります。
戸籍の請求は、本籍地のある市区町村役場に対して行います。本籍が移動している場合は、そのたびに管轄が変わるため、複数の役所に請求が必要になることもあります。
相続財産は?固定資産税の納税通知書で不動産を確認する
空き家を含む相続手続きを進めるに被相続人の不動産を確認する方法は、毎年5月頃に市区町村から届く固定資産税の納税通知書です。1月1日時点で不動産を所有している人に送付される書類で、土地や建物の所在地や評価額などが一覧で記載されています。
納税通知書を見れば、不動産がどの市町村にあるのか、どんな建物なのかがわかります。たとえば、「実家の隣の空き地も名義は父だった」「山林も持っていたことを初めて知った」といったケースも少なくありません。
もし通知書が見つからない場合は、市区町村の役所で名寄帳(なよせちょう)を請求します。名寄帳は、市町村内で所有していたすべての不動産を一覧で確認できます。
誰が何を相続する?相続人全員で遺産分割協議を行う
遺産分割協議は、相続人全員が集まり亡くなった人の財産を「誰が」「何を」「どれだけ」相続するかを話し合うことです。遺産分割協議では相続人全員の合意が必要であり、誰か一人でも参加しなかった場合、協議は無効です。遠方に住んでいる人や日程調整が難しい人がいる場合、書面などで分割内容の意思確認が必要です。
協議がまとまったら、遺産分割協議書に内容をまとめます。相続人全員の署名と実印による押印が必要で、後の相続登記で遺産分割協議書を提出します。
不動産は金額が大きく、共有にするのか売却して現金で分けるのかなど、考え方の違いが出やすい財産です。話し合いがスムーズに進まない場合は、弁護士に相談することも1つの方法です。
自分でもできる?相続登記の進め方
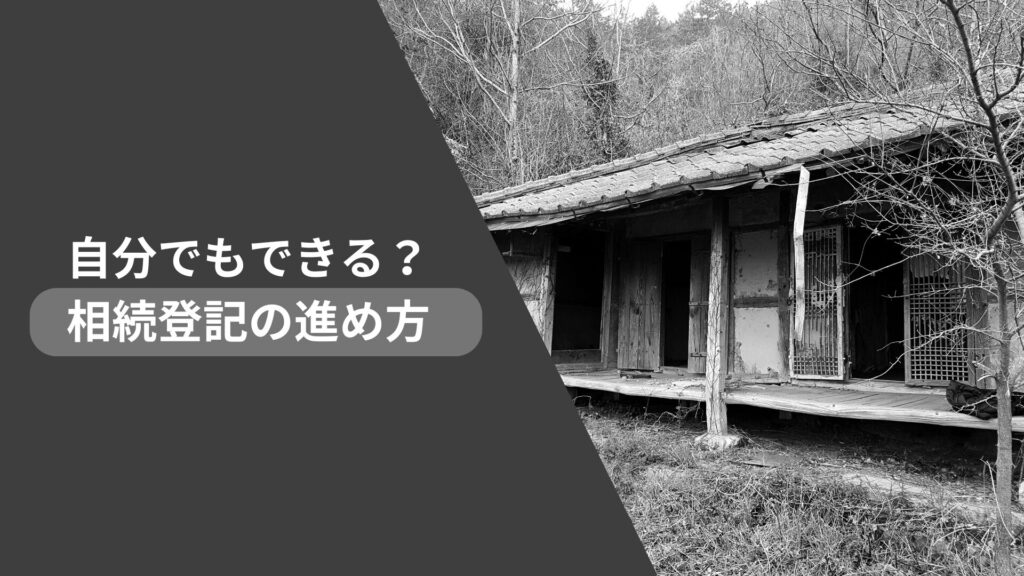
相続登記は専門家に依頼しないとできないと思われがちですが、実は相続人自身で進めることも可能です。しかし、初めて相続を経験する方にとっては手続きを進めるのは簡単ではありません。ここでは、自身で行う相続登記の進め方を解説します。
- 自分で進める場合は時間がかかる
- 相続登記の専門家である司法書士に依頼する
自分で進める場合は時間がかかる
相続登記は、相続人自身で行うことも可能です。相続登記の申請には、次の書類を揃える必要があります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
- 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を相続する相続人の住民票
- 遺産分割協議書(または遺言書)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産の固定資産評価証明書
- 登記申請書
申請書類に不備があると、市区町村役場や法務局に何度も足を運ぶ必要があり、差し戻されて手続きがやり直しになる可能性もあるため注意が必要です。初めて手続きをする場合は、法務局の窓口で事前相談を受けることをおすすめします。必要書類や手続きの流れを丁寧に教えてもらえるため、安心して進められます。
相続登記は自身で進められますが、時間に余裕がない方や書類の内容に不安がある方は、司法書士への依頼を検討しましょう。
相続登記の専門家である司法書士に依頼する
司法書士は不動産登記の専門家であり、相続に伴う複雑な書類作成や法務局への申請を代行してくれます。次のようなケースでは、司法書士に依頼するのが安心です。
- 不動産が複数ある
- 現状と登記が合っていない不動産がある
- 相続人が多い、または関係が悪い
- 相続人に兄弟姉妹や甥・姪が含まれる
- 不動産が遠方にあり登記の対応が難しい
- とにかく早く登記を済ませたい
司法書士に依頼すれば、戸籍の取得や書類のチェックも含めてサポートしてもらえるため、手続きがスムーズに進みます。仮に書類に不備があったとしても代わりに対応するため、相続人には負担がありません。
司法書士報酬は不動産の数や地域によりますが、1件あたり5万~15万円程度が目安です。登記申請に必要な登録免許税とは別にかかるため、事前に見積もりを取りサービス内容と合わせて比較しましょう。自分で手続きすれば費用は抑えられますが、時間・労力・リスクを考えると、「費用対効果」で専門家に任せる価値は十分にあります。
相続登記で困ったケース

相続登記には期限があり、手続きが煩雑なうえ放置すると相続人に不利益なケースがあります。ここでは、実際に相続登記で困った3つの事例を紹介します。
- 期限内に相続登記が難しい場合は「相続人申告登記」
- 安くなる?登録免許税の確認方法
- 相続登記しないと空き家を手放せない
期限内に相続登記が難しい場合は「相続人申告登記」
2024年4月から相続登記が義務化されましたが、期限内に相続登記を完了させるのが難しいケースも少なくありません。そんなときに活用できる制度が「相続人申告登記」です。
相続人申告登記とは、「私はこの不動産の相続人です」と法務局に申し出ることで、登記の義務をいったん果たしたことにできる仕組みです。手続きをしておけば、たとえ遺産分割がまだ済んでいなくても、3年以内の登記義務違反にはなりません。相続人申告登記のメリットは、以下のとおりです。
- 1人でも申告可能:他の相続人の同意は不要
- 押印・電子署名不要で簡単な書類とWeb申請で対応可
- 登録免許税がなく、無料で義務を履行できる
- 必要書類が少なく、相続関係を示す戸籍の一部で申請可能
たとえば、「兄弟姉妹が多く、連絡すら取れない」「不動産が数代前の名義になっている」などの事情があっても、相続人であることが確認できれば、相続人申告登記だけ先に済ませることが可能です。
ただし、相続人申告登記はあくまで「義務を履行した」とみなされるための制度であり、不動産の名義を自分に変更できるわけではありません。そのため、売却など所有者でないといけない手続きをするには、改めて正式な相続登記が必要です。
安くなる?登録免許税の確認方法
相続登記を行う際には、申請時に登録免許税が必要になります。登録免許税は、相続する不動産の「固定資産税評価額」に0.4%を掛けて算出します。
不動産の評価額は、毎年5月ごろに届く「固定資産税課税明細書」で確認できます。もし手元に明細書がない場合は、市区町村役場で「固定資産評価証明書」を取得することで確認できます。
登録免許税は免税措置があり、次の条件を満たすと免除されます。
- 相続した土地の評価額が100万円以下の場合
- 登記がされないまま相続人が死亡し、その相続人を経由する登記をする場合
ただし、免税措置は土地に限定されており、建物には適用されません。
登録免許税は、登記申請時に収入印紙を登記申請書に貼付する形で納付します。収入印紙への割り印は必要ありません。また、課税価格に税率を掛けて100円未満を切り捨てた金額が納付する登録免許税です。
相続登記しないと空き家を手放せない
名義が亡くなった方のままでは不動産の所有権が正式に移っていないため、第三者に対して売却できません。相続登記をせずに空き家を放置してしまうと、次のような問題が起こります。
- 不動産の売却ができない
- 賃貸に出すことも難しい
- 国や自治体への寄付も受け付けられない
- 空き家管理の責任だけが残る
管理や固定資産税の負担だけが続き、時間の経過とともに相続人の数が増えていきます。たとえば、親から相続した不動産について何もしないまま自分が亡くなると、次の相続人である子どもに権利が移ります。法定相続人が多くなり「全員の同意」が必要になっても、連絡が取れない親族がいたり、話がまとまらなかったりして売却ができないというケースも少なくありません。
「売却したい」「手放したい」と思っても、登記をしていなければ一歩も進めません。空き家の将来的な選択肢を広げるためにも、まず相続登記を済ませることが重要です。
空き家の管理は相続人に義務がある

相続を放棄しても状況によっては管理義務が残るケースがあり、何もせずに空き家を放置すると思わぬ費用を請求される可能性があります。ここでは、空き家を相続した際に知っておくべき管理責任を解説します。
- 相続放棄しても管理義務が残る可能性がある
- 管理が行き届かないと「特定空き家」の認定を受けて費用負担が増える
- 空き家を売却や寄付できないか検討する
相続放棄しても管理義務が残る可能性がある
相続放棄をしたら空き家を管理する必要がないと思っていませんか?実は、相続放棄をしても空き家の管理義務が残るケースがあります。
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。民法第940条(相続の放棄をした者による管理)
相続を放棄した人でも荷物をおいて空き家を使っていたり、鍵を持って自由に出入りできる状態であると占有とみなされ、管理を続けなければいけません。
管理義務を免れるには、自分以外の相続人が相続するか家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てる必要があります。
放棄した場合についてはこちらの記事「相続放棄したら空き家はどうなる?管理義務と固定資産税6倍増を回避する方法」も参考にしてください。
管理が行き届かないと「特定空き家」の認定を受けて費用負担が増える
空き家の放置が続くと、行政から「特定空き家」に指定される可能性があります。特定空き家とは、倒壊の危険や衛生上の問題など、周囲に悪影響を及ぼす空き家のことです。指定されると、所有者は以下のような不利益を受ける可能性があります。
- 解体などの指導・勧告・命令
- 命令等に従わなければ最大50万円の過料が科される
- 住宅用地の特例が適用されなくなり固定資産税が最大6倍に増額
行政の強制措置である代執行がなされると、費用は所有者が負担します。実費全てが徴収され、税金と同じく強制徴収される可能もあります。将来的に高額な費用負担を強いられることになるため、空き家は放置せず早めに対応しましょう。
空き家を売却や寄付できないか検討する
管理が負担になっている空き家は、手放す方法も検討してみましょう。立地が良い又は建替えができる土地であれば、売却できる可能性があります。不動産会社に相談し、相場や売却の可否を確認してみましょう。
売却が難しければ、自治体への寄付があります。条件が合うかを地元の自治体に確認してみましょう。相続土地国庫帰属制度は、一定の条件を満たせば土地を国に引き取ってもらえます。空き家を取り壊して更地にする必要があり所有者にとっては負担がありますが、所有者不明土地をなく土地を有効活用する手段として注目されています。
参考:法務省「相続土地国庫帰属制度について」
空き家を持ち続けるリスクと管理コストを比較し、最適な選択肢を見極めることが大切です。
まとめ:空き家の相続登記は専門家に任せるのが安心
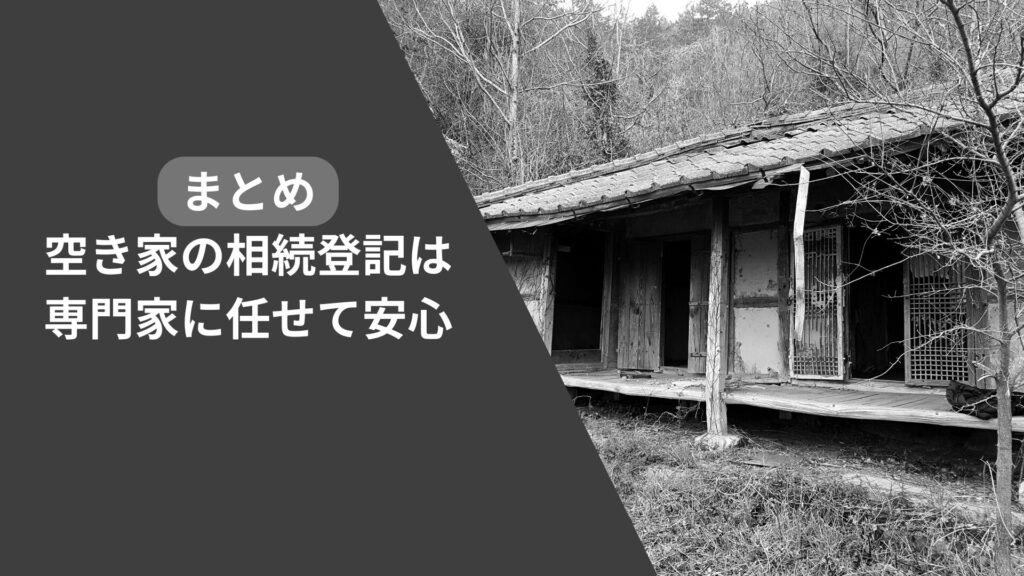
不動産の名義変更を怠ると、売却ができないばかりか空き家の管理責任や高額な費用負担を背負うリスクがあります。遠方にある空き家を相続するケースでは「遺産分割がまとまらない」「登記が面倒で放置してしまう」といった問題が起こりやすいです。
相続登記は義務化されたので、司法書士へ依頼する選択肢を知っておけば無理なく対応を進められます。また、空き家を売却や寄付などで手放す方法も、事前に調べておくことで安心できます。
あとでやろうと放置せず、相続登記と空き家管理に関する対応を早めに始めましょう。自分や家族にとって最も負担の少ない方法を見つけることが大切です。