空き家を相続放棄するには、決められた手続きの流れと注意点を理解しておくことが欠かせません。なぜなら、相続放棄には期限があり方法を誤ると「放棄したはずなのに管理責任を問われる」などのトラブルにつながる可能性があるからです。相続放棄をしても、空き家の管理責任から完全に解放されるわけではありません。
たとえば、家庭裁判所での手続きには必要書類や流れがあり、受理されるまでにステップがあります。期限内で放棄するには手続きを事前に把握しておく必要があり、正しく理解していないと後から思わぬ負担が発生する可能性があります。
この記事では、相続放棄の手続きの流れだけでなく、注意点や他の対処方法を解説します。相続した空き家の扱いに困っている方は、最後まで読んで参考にしてください。
- 空き家を相続放棄するための具体的な手続きの流れがわかる
- 具体的にどのくらいの手続き費用がかかるかわかる
- 相続放棄をする際の注意点を知る
- 相続放棄以外の空き家対処法がわかる
空き家を相続放棄する手続きの流れ
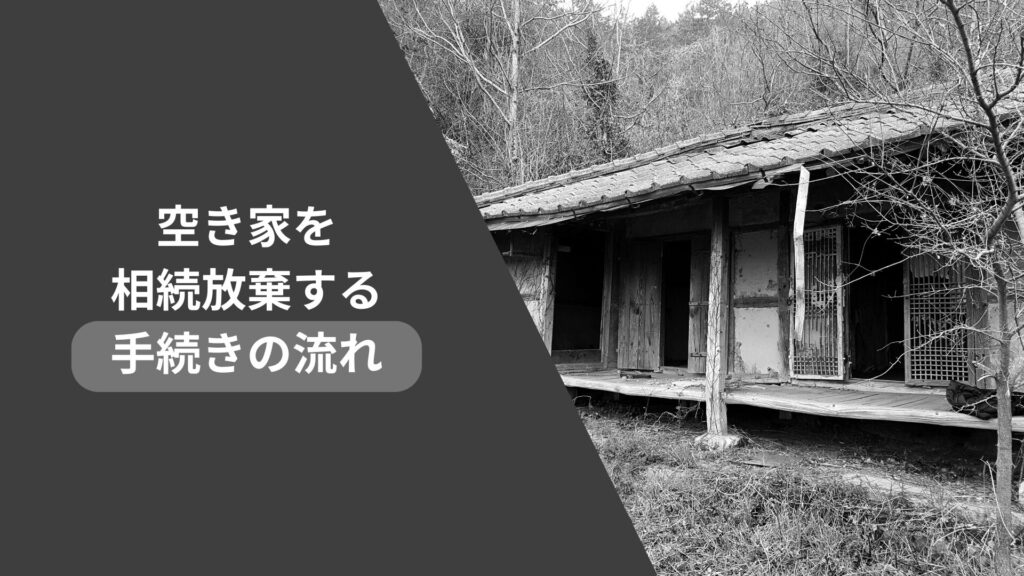
相続放棄は家庭裁判所に申立てを行うことで成立しますが、全体の流れをあらかじめ理解しておくことが大切です。ここでは、実際に相続放棄が受理されるまでの手順を説明します。
- 1.必要な書類を集める
- 2.相続放棄の申述書を作成する
- 3.提出する家庭裁判所を確認する
- 4.裁判所からの照会書を返送する
- 5.相続放棄申述受理通知書を受領する
1.必要な書類を集める
相続放棄を進めるにあたり、最初に行うのが必要書類の収集です。提出する書類は、相続人が「相続を放棄する意思」を裁判所に示すための根拠となるもので、不備があると受理されません。主な書類は以下のとおりです。
- 亡くなった方の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
- 亡くなった方の住民票の除票または戸籍附票
- 相続放棄をする人の戸籍謄本
- 相続放棄申述書(後述)
戸籍や住民票は、市区町村役場で取得できます。遠方に住んでいる場合は郵送請求も可能です。ただし、相続関係が複雑な場合は、複数の戸籍をさかのぼって取得する必要があり、時間がかかることもあります。
特に注意すべき点は、相続放棄の期限が3ヶ月以内と決められていることです。書類の取り寄せに日数を要するため、早めの準備が欠かせません。もし取り寄せに迷った場合や時間が足りない場合は、専門家に代行を依頼することも可能です。
2.相続放棄の申述書を作成する
次に、家庭裁判所に提出する正式な申立書である「相続放棄申述書」を作成します。
申述書には、申述人(相続放棄をする人)の氏名・住所・生年月日・被相続人との関係を記載します。さらに、放棄の理由や申述人の署名捺印も必要です。家庭裁判所のホームページから書式をダウンロードでき、記入例もあるため自分で作成できます。
また、申述書には800円分の収入印紙を貼付し、裁判所が指定する額の切手を同封します。切手代は裁判所ごとに異なるため、必ず事前に確認しましょう。
注意点として、誤字脱字や記入漏れがあると書類が差し戻される可能性があります。その場合、手続きが遅れ、3ヶ月の期限を超えてしまう危険もあります。記入に不安がある場合は、司法書士や弁護士に確認してもらうのも一つの方法です。
3.提出する家庭裁判所を確認する
申述書と必要書類がそろったら、管轄の家庭裁判所に提出します。提出先は「亡くなった方が最後に住んでいた住所地」を管轄する家庭裁判所と法律で定められています。たとえば、亡くなった方が東京都内に住んでいた場合は、その地域を担当する家庭裁判所が窓口になります。
提出方法は2通りあります。
- 家庭裁判所の窓口へ直接持参する
- 郵送で提出する
郵送する際は、記録が残る「レターパックプラス」や簡易書留などを利用するのがおすすめです。万一の紛失に備え、控えとしてコピーを取っておくと安心です。
重要なポイントは、提出が期限内に完了しているかどうかです。裁判所が書類を受理した日ではなく、「提出した日」が基準となるため、余裕をもって準備しましょう。
4.裁判所からの照会書を返送する
申述書を提出すると、通常は10日前後で家庭裁判所から「照会書」という書類が届きます。照会書は、相続放棄が本当に本人の意思に基づいているかを確認するための質問票のようなものです。
記載される内容は、以下のとおりです。
- 相続放棄を決めた理由
- 相続財産を処分していないか(単純承認にあたらないか)
- 放棄の意思が自分の判断によるものか
上記に回答し、裁判所に返送します。回答は簡潔に、事実を正しく書くことが大切です。
注意点として、相続開始後に財産を使ったり、売却したりすると「相続放棄はできない」と判断される場合があります。単純承認と呼ばれ、借金なども含めてすべて引き継ぐ扱いとなってしまいます。心当たりがある場合は、専門家に相談してから回答すると安心です。
5.相続放棄申述受理通知書を受領する
照会書を返送し、裁判所が内容を確認して問題がなければ、最終的に「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。この通知書を受け取った時点で、相続放棄が正式に成立します。
通知書は再発行できないため、紛失しないように保管してください。普段の生活で提出を求められることは少ないですが、債権者から支払いを請求された場合や金融機関での手続きに備え、別途「相続放棄申述受理証明書」を家庭裁判所に請求しておくと安心です。証明書は1通あたり150円程度の収入印紙で発行可能です。
これで空き家の相続放棄手続きは完了します。手続き自体は数週間から1ヶ月程度で終わりますが、期限内に正確な書類を提出できるかどうかが最大のポイントとなります。
空き家を相続放棄する際に必要な費用
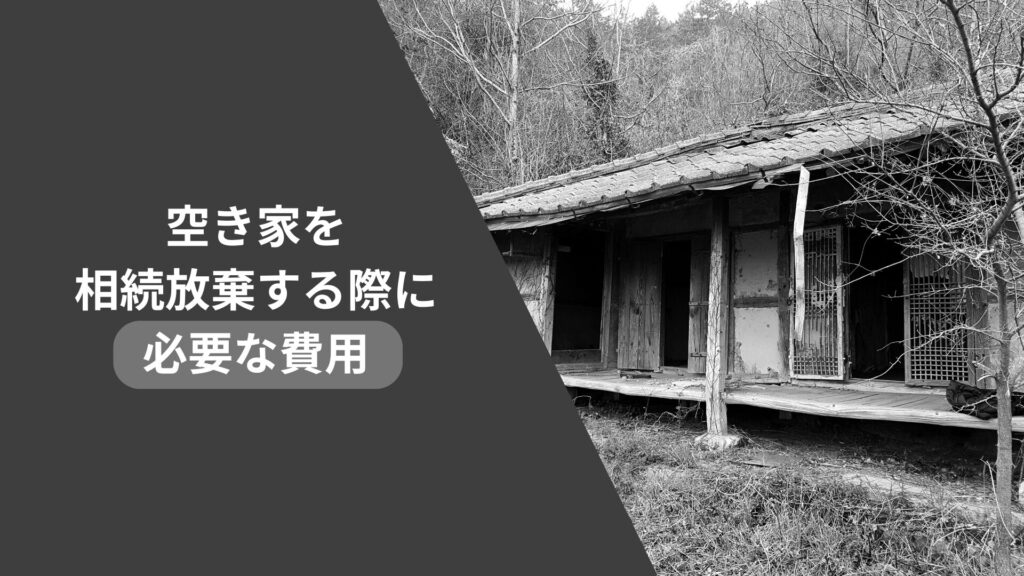
相続放棄の手続きは、複雑そうに見えて実際に裁判所へ提出する費用自体はそれほど高額ではありません。しかし、相続人の人数や財産の状況によって必要になる費用は変わります。ここでは空き家の管理義務を解消するためにかかる費用を具体的に見ていきましょう。
- 申述書の提出の際にかかる費用
- 相続財産清算人の選任の際に裁判所に納める費用
申述書の提出の際にかかる費用
相続放棄の手続きを自分で行う場合、裁判所に提出する際に必要となる費用はおおむね3,000円〜5,000円程度に収まります。思ったよりも少額で済むため、「手続きそのものに大きなお金はかからない」という点は安心材料になるでしょう。内訳は、次のとおりです。
| 項目 | 金額 | 取得場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 収入印紙 | 800円 | 郵便局や法務局 | 申述する手数料 |
| 郵便切手 | 400~500円 | 郵便局 | 裁判所からの連絡用 |
| 戸籍謄本 | 450円程度 | 市区町村役場 | 相続人本人の証明 |
| 戸籍(除籍・改製原戸籍) | 750円程度 | 市区町村役場 | 被相続人の証明 |
| 住民票除票または戸籍附票 | 300円程度 | 市区町村役場 | 被相続人の証明 |
上記を合計すると3,000円前後になります。しかし、相続人の人数や相続関係が複雑な場合、必要書類の数が増える場合があります。役所まで出向くための交通費や平日に休みを取る手間も考慮しておくとよいでしょう。
書類の取り寄せや申述書の作成に不安がある場合は、司法書士や弁護士に依頼するという選択肢もあります。専門家に依頼すれば正確に進められますが、別途3万〜5万円程度の報酬が必要になる点を理解しておきましょう。
相続財産清算人の選任の際に裁判所に納める費用
相続放棄をしたとしても、状況によっては空き家の管理義務からすぐに解放されないことがあります。その場合に利用されるのが「相続財産清算人」という制度です。
相続財産清算人とは、亡くなった方の財産を整理・清算する役割を裁判所から任される人を指します。清算人が選任されれば、相続人が空き家の管理を続ける必要はなくなり、責任を免れます。
清算人制度を利用するには、家庭裁判所へ申し立てを行い、一定の費用を納めなければなりません。具体的には以下のような費用がかかります。
- 収入印紙代:800円(申立書に貼付)
- 予納金(裁判所に納める費用):数十万円〜100万円程度
清算人が業務を行うための費用を前払いするもので、財産の規模や状況によって金額は大きく変動します。
この「予納金」が非常に高額である点が最大の特徴です。たとえば、空き家の価値が低くても、清算人を選任するためにまとまった金額が必要になることが多いため、費用負担は無視できません。
そのため、相続財産清算人の申立ては「どうしても自分では管理できない」「他に相続人がいない」などのケースで選ばれることが多く、慎重な判断が必要です。費用面も含めて現実的に利用できるかどうかは、弁護士など専門家と相談しながら決めると安心です。
相続放棄の5つの注意点

相続放棄は「借金を受け継がないための手段」として有効ですが、安易に手続きを進めてしまうと後から思わぬ不利益を被ることがあります。ここでは、相続放棄で注意すべき5つのポイントを解説します。
- 相続放棄の期限は「3ヶ月以内」
- 放棄後は撤回・取消が難しい
- 管理義務が残るケースがある
- 相続した空き家には住めない・荷物を置いてはいけない
- 空き家のみを放棄できない
相続放棄の期限は「3ヶ月以内」
相続放棄には「期限」があり、原則として被相続人(亡くなった方)が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に手続きを行わなければなりません。この期間を「熟慮期間」と呼びます。熟慮期間を過ぎると、自動的に相続を承認したとみなされ、負債も含めてすべての遺産を受け継ぐことになります。
ただし、財産の調査に時間がかかる場合や、遺産の有無がすぐに確認できない場合には、家庭裁判所に「期間の延長」を申し立てることが可能です。3ヶ月の期限を過ぎてしまった後でも、特別な事情(亡くなったことを知らなかった、相続財産が全くないと信じていた等)があれば相続放棄が認められるケースもあります。とはいえ、原則は厳格に「3ヶ月以内」ですので、相続財産の有無に関わらず早めに調査を始めることが大切です。
放棄後は撤回・取消が難しい
一度家庭裁判所に申述を行い相続放棄が受理されると、基本的には撤回できません。たとえその後に大きな財産が見つかっても、放棄の取り消しは認められないのが原則です。例外として、詐欺や強迫、重大な勘違い(錯誤)によって放棄をしてしまった場合には、取消が可能となることもありますが、実務上はごく限られたケースです。
そのため、相続放棄を検討する際には、プラスの財産とマイナスの財産の両方を可能な限り調べた上で判断する必要があります。「あとから撤回すればよい」という考えは通用しない点に注意しましょう。
管理義務が残るケースがある
相続放棄をしたからといって、すべての責任から解放されるわけではありません。民法940条では、放棄した相続人であっても「現に相続財産を占有している場合」には、その財産を適切に保存しなければならないと定めています。
たとえば、亡くなった方の自宅に住んでいた相続人が放棄した場合、その家を相続財産清算人などに引き渡すまでの間、建物を損なわないように管理する義務があります。この義務を怠ると、第三者に損害を与えたとして責任を問われることもあります。逆に、亡くなった方の家が誰も住んでいない「空き家」で、相続人が占有していない場合には、保存義務は発生しません。
相続した空き家には住めない・荷物を置いてはいけない
相続放棄をすると、「初めから相続人でなかった」と扱われるため、その空き家を自由に使うことはできません。放棄後に住み続けたり、荷物を置いたりすることは「財産を処分した行為」とみなされる可能性があり、場合によっては相続放棄そのものが無効とされてしまいます。
また、空き家を勝手に利用すると、管理義務の履行とも矛盾し、トラブルの原因となります。放棄を選んだ場合は「一切手を付けない」ことが鉄則です。住む予定がない場合でも、不要な荷物の一時保管などは避けるべきでしょう。
空き家のみを放棄できない
「空き家だけ放棄して、その他の財産は受け取りたい」という選択はできません。相続放棄は財産ごとではなく「相続人としての立場全体」を放棄する制度だからです。そのため、空き家の相続を避けたい場合には、他の資産も含めて一切を放棄する必要があります。
もし空き家の負担を避けつつ、他の財産を受け取りたい場合は、相続放棄ではなく「遺産分割協議」で調整する方法を検討する必要があります。ただし、この場合は債権者からの請求を免れることはできないため、負債が多いケースでは根本的な解決にはなりません。
相続放棄以外にできる空き家の対処方法5選

相続放棄を選ばなくても、空き家の負担を軽減したり手放したりする方法はいくつか存在します。自身や家族の状況に合った方法を知っておけば、不要なリスクを避けられます。ここでは、具体的な対処法を解説します。
- 売却する
- 贈与する
- 更地にして活用する
- 相続土地国庫帰属制度を活用する
- 寄附する
売却する
売却は、主に仲介と買取の2つの方法があります。仲介は、不動産会社が買主を探すため時間がかかる一方で、成約価格を高くできる期待が持てます。買取は、不動産会社が買主となるため現金化までが早く、管理や解体を避けたいときに有効です。
空き家を売却すると、固定資産税や維持管理などの手間から解放されます。相続税の申告期限から3年以内に売却した場合に使える「取得費加算の特例」があるため、譲渡益の税負担を抑えられる可能性もあります。
売却は、不動産会社に査定を依頼することから始めましょう。空き家の残存物や隣地との境界を手入れしておくとスムーズに進みます。雨漏りやシロアリなど空き家自体に不具合があるときは、事前に状況を把握しておくと良いでしょう。
贈与する
空き家を親族や近隣の人へ無償で引き渡す方法として、贈与があります。所有し続ける必要がなくなるため、固定資産税や管理の負担から解放される点がメリットです。
ただし、贈与は無償譲渡であっても手続き等で費用がかかります。不動産の名義を変えるには登録免許税や不動産取得税がかかります。また、空き家を無償で受け取った側が贈与税の申告をしなくてはいけません。時価より大幅に安い金額で譲渡したとみなされると、差額分が贈与と判断されます。築年数が経っているから価値がないと思っていても、事前に費用を試算しておくことが重要です。
更地にして活用する
空き家を解体して土地のみで活用する方法です。たとえば、以下の用途が考えられます。
- 月極駐車場
- トランクルーム
- 太陽光設備
- 資材置き場
- 事業用地
建物の老朽化が進み利用が難しい場合、土地のみの利用へ切り替えると活用できる可能性があります。しかし、解体費用の負担や土地の固定資産税の増加に注意しなくてはいけません。
個別具体的な話になるので、税理士などの専門家に相談して、活用案の収支試算をしてみましょう。
相続土地国庫帰属制度を活用する
「相続土地国庫帰属制度」は、相続で取得した土地が一定の要件を満たした場合、負担金を納付して国に引き取ってもらう仕組みです。建物が残っている土地は対象外のため、原則解体してから申請します。建物が無くても、境界が明らかでなかったり他人が使用していたりする土地は申請できません。
制度を利用する流れは、以下のとおりです。
- 法務局へ相談
- 申請
- 要件審査
- 承認
- 負担金の納付
- 国庫帰属
負担金は原則20万円ですが、立地によっては面積により負担金が増額します。負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に移転します。手続きの全てを代理人に依頼することはできず、申請は本人と法定代理人のみができるので、注意が必要です。
寄附する
自治体や公益法人へ無償で提供する方法です。公共施設や防災拠点、緑地などの用途に合致し、維持管理の見込みが立つ場合に限り、受け入れが検討されます。使途が想定できない土地や管理が重い物件は、原則として受け付けられません。
自治体によって取り扱いが異なるので、進める際は事前相談して確認してみましょう。土地に関する登記簿や図面などの資料を持っていくとスムーズです。
まとめ:空き家相続放棄は早めの手続きと専門家相談が安心
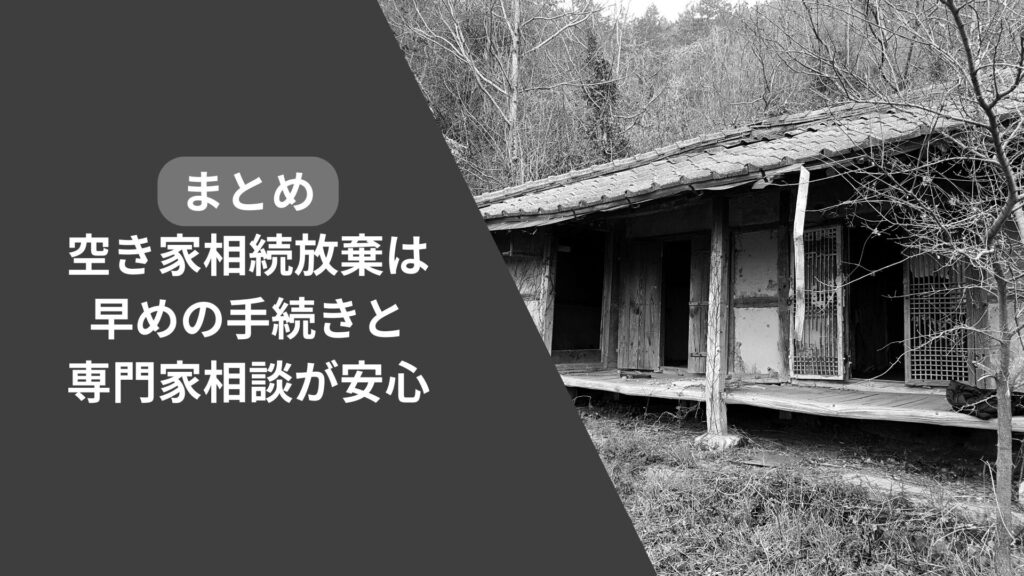
空き家を相続放棄するには、3ヶ月以内で必要書類をそろえ、家庭裁判所へ申立てを行います。受理されれば相続放棄は成立しますが、放棄後の撤回は難しいため、事前に財産や負債を十分に調査する必要があります。
費用面では、申述にかかる実費は数千円程度と大きな負担はありませんが、状況によっては相続財産清算人の選任に数十万円以上が必要になることもあります。自身での対応が不安であれば、司法書士や弁護士へ依頼しましょう。
しかし、空き家を手放す方法は相続放棄だけではありません。売却や相続土地国庫帰属制度などの選択肢もあり、ケースによって適した方法は異なります。
空き家の相続放棄や処分は「期限・費用・手段」を総合的に理解したうえで判断することが不可欠です。迷った場合は、早めに専門家へ相談することでリスクを避け、安心して最適な方法を選択できるでしょう。
