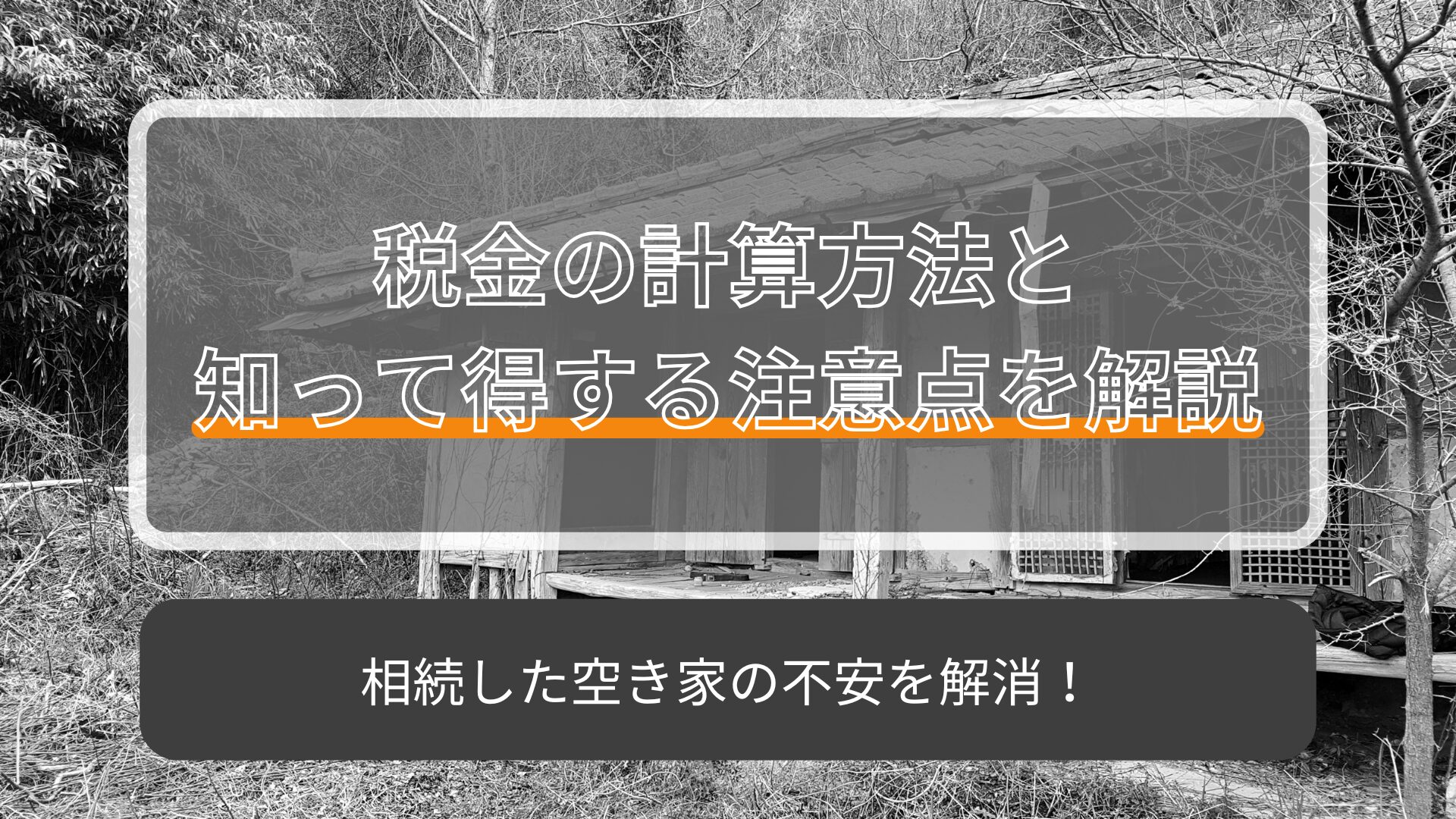「相続した実家が空き家で対応に困っている」という方もいるのではないでしょうか。とりあえず保留にしておこうと放置していると、思わぬ税金が発生するリスクがあります。
空き家は相続税や固定資産税など、複数の税金が関わってきます。管理を怠って「特定空き家」に指定されると、固定資産税が最大6倍になる可能性があります。一方で、条件を満たせば税負担を軽減できる制度があります。
- 空き家を相続したときに発生する主な税金がわかる
- 相続税の負担を軽減する節税制度の内容と適用条件がわかる
- 空き家を放置することによるリスクと取るべき対応策がわかる
この記事では、空き家を相続したときに知っておくべき税金の基本から、使える制度、注意点までをわかりやすく解説します。「知らなかった」で損をしないために、今のうちに正しい知識を身につけておきましょう。
空き家を相続したらかかる3つの税金

たとえ住む予定がなくても、空き家を持っているだけで課される税金があるため、放置してしまうとコストが膨らんでいきます。
- 相続税
- 登録免許税
- 固定資産税
ここでは、空き家を相続したときに発生する代表的な3つの税金についてわかりやすく解説します。
相続税
空き家を相続すると、多くの場合で相続税が発生します。相続税は、亡くなった方(被相続人)の財産を受け継ぐときにかかる税金で、現金や預貯金だけでなく土地や建物などの不動産も課税対象に含まれます。
相続税を減額できる「小規模宅地等の特例」制度を思い浮かべる方もいるでしょう。しかし、すでに空き家になっている状態では、この特例の要件を満たせない可能性が高いです。結果として相続税が減額できず、高く感じます。
相続税は、遺産全体の金額に対して課税されます。空き家単体で見るのではなく、他の財産と合わせた総額を早めに把握しておきましょう。
登録免許税
亡くなった方から相続人へ不動産の名義を変更する相続登記を行う際に、法務局に納める登録免許税が必要です。登録免許税の金額は、相続する不動産の固定資産税評価額の0.4%です。たとえば、固定資産税評価額が1,000万円の空き家であれば、登録免許税は4万円かかります。
2024年4月から相続登記は義務化されました。相続によって不動産を取得した場合は3年以内に登記を申請しなければいけません。正当な理由がなく相続登記しない場合は、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が科される可能性があります。
一方で、登録免許税の一部免税措置があります。相続する土地の評価額が100万円以下であれば、2027年3月31日までに登記を行うことで登録免許税が免除されます。
固定資産税
空き家を相続した場合、毎年かかり続けるのが固定資産税です。土地や建物を持っている人に課される税金で、毎年1月1日時点の所有者に対して各自治体から納税通知書が送られます。
空き家であっても、建物と土地のどちらにも固定資産税は発生します。名義変更が終わっていない場合でも、相続人が実質的な所有者として固定資産税を納めなくてはいけません。
また、空き家を放置したままにしておくと、固定資産税が高くなる可能性があります。通常は「住宅用地の特例」により、土地にかかる固定資産税が最大で6分の1まで軽減されます。しかし、管理が行き届かず「特定空き家」に指定されると、特例の対象から外され固定資産税が最大6倍になるケースがあります。
空き家の相続税の計算方法

空き家を相続したら、実際にいくら相続税がかかるのかが気になる方は多いのではないでしょうか。相続税の金額は、土地・建物それぞれの評価方法によって大きく変わります。
- 土地:路線価方式
- 土地:倍率方式
- 建物を含めた計算例
土地の評価方法には「路線価方式」と「倍率方式」の2種類があります。ここでは、土地の評価方法ごとの計算方法に加え、建物を含めた相続税の具体例まで解説します。
土地:路線価方式
路線価とは、国税庁が毎年公表している道路に面する標準的な宅地の1㎡あたりの評価額のことです。国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」または一般財団法人資産評価システム研究センターが提供している「全国地価マップ」で確認できます。
たとえば、路線価が「300」と表示されていれば、道路に面した土地の1㎡あたりの評価額は30万円です。相続税評価額を算出するには、次の計算式を用います。
土地の評価額=路線価×補正率×土地の面積(㎡)
補正率とは、土地の形や使い勝手などを考慮して調整される数値で、「奥行価格補正率」や「間口狭小補正率」などがあります。
土地:倍率方式
相続した空き家が郊外や地方にあり路線価が定められていない場合は、土地の相続税評価額を倍率方式で算出します。倍率方式は、土地の固定資産税評価額に評価倍率を掛けるシンプルな計算方法です。
土地の相続税評価額 = 固定資産税評価額 × 評価倍率
毎年公表されている評価倍率は、国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で確認できます。土地の地目ごとに倍率が記載されているので、該当するものをチェックしましょう。
建物を含めた計算例
空き家を相続した場合、どのように税額が決まるのかを具体的な計算例で解説します。
- 土地(300㎡):路線価 30万円/㎡、補正率 1.0 → 評価額 9,000万円
- 建物(固定資産税評価額):2,000万円
- 現金:3,000万円
- 負債・葬儀費用:借入金:500万円、葬儀費用:200万円
- 法定相続人:1人(子1人)
ステップ1:正味の遺産額を計算する
正味の遺産額 = 財産合計 - 負債・葬儀費用
=(9,000万円+2,000万円+3,000万円)-(500万円+200万円)
= 1億3,300万円
ステップ2:基礎控除を計算する
基礎控除 = 3,000万円+(600万円 × 相続人の数)
= 3,000万円+600万円 = 3,600万円
課税遺産総額 = 正味の遺産額 - 基礎控除
= 1億3,300万円-3,600万円 = 9,700万円
ステップ3:相続税を計算する
法定相続分(1人なので全額):9,700万円
相続税速算表によると、1億円以下は税率30%、控除額700万円
相続税額 = 9,700万円 × 30%-700万円
= 2,910万円-700万円
= 2,210万円
同居や一定の条件を満たして「小規模宅地等の特例」が適用できる場合、土地評価額が最大80%減額されます。
土地評価額:9,000万円 → 80%減額なら1,800万円
この場合、全体の評価額は
1,800万円(土地)+2,000万円(建物)+3,000万円(現金)= 6,800万円
正味の遺産額= 6,800万円-700万円(借入・葬儀費用)= 6,100万円
課税遺産総額= 6,100万円-3,600万円= 2,500万円
相続税= 2,500万円 × 15%-50万円(控除)= 325万円
今回の例では、特例なしで2,210万円、特例ありなら325万円と、相続税に1,885万円もの差が生まれました。相続税は財産の種類によって変動するので、事前に評価額を把握しておくだけでも節税に対応しやすくなります。
空き家の相続税を対策する方法

何も対策をしなければ、相続税など税金が高額になることも珍しくありません。しかし、適切な制度や特例を理解し、活用することで税負担を大きく減らすことが可能です。
- 小規模宅地等の特例を適用する
- 相続後に売却して特例を適用する
- 相続前に売却する
ここでは、さまざまなタイミングで使える節税対策を解説します。
小規模宅地等の特例を適用する
相続税を大幅に減らせる制度として注目されている「小規模宅地等の特例」は、土地の評価額を最大80%まで減額できる可能性があり、数百万円の節税効果が期待できます。たとえば、評価額が1億円の土地でも特例を適用すると2,000万円の評価に抑えられるケースがあります。土地の評価が下がれば、結果として相続税の課税額が下がります。
この特例は、相続する土地の「用途」によって次のように分類されます。
| 用途区分 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 | 330㎡ | 80% |
| 貸付事業以外の事業用の宅地等 | 400㎡ | 80% |
| 貸付事業用の宅地等 | 200~400㎡ | 50~80% |
被相続人の自宅として使われていた土地の場合、相続人が誰かによって適用条件が変わります。
| 取得者 | 要件 |
|---|---|
| 配偶者 | 無条件で適用可 |
| 同居していた親族 | 相続時点で同居しており、現在も住み続けている |
| 別居していた親族 | 次の条件を全て満たすこと・被相続人に配偶者や同居親族がいない・相続前3年以内に自分名義や配偶者名義の住宅に住んでいない・相続後も引き続き土地を保有している |
小規模宅地等の特例はとても有利な制度ですが、要件を満たさないと適用されません。別居していた場合は細かい条件があるため、判断が難しいケースがあります。適用可否が不明な場合は、税理士に相談してみましょう。
相続後に売却して特例を適用する
空き家を相続しても使う予定がない場合、売却を検討する方は「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」を検討しましょう。譲渡所得から最大3,000万円を控除できるため、税負担を大幅に軽減できます。
この特例は以下の要件を全て満たす必要があります。
- 令和9年(2027年)12月31日までに売却する
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋である
- 区分所有建物でない(マンション等は対象外)
- 被相続人が一人暮らしをしていた住宅であること
- 相続から売却まで、空き家を誰も住居・事業・貸付に使っていないこと
- 売却代金が1億円以下であること
- 譲渡は相続開始から3年を経過する年の12月31日までに完了している
- 他の特例の適用を受けていないこと
- 親族などへの売却でないこと
相続人が3人以上いる場合は、1人あたりの控除額が2,000万円に制限されました。相続人が多い場合は適用を最大限受けられない可能性があるため、事前に税理士と相談し分割や売却方法を決めることが重要です。
相続前に売却する
相続前に売却することで使える特例は、以下の2つがあります。
- 居住用財産の3,000万円特別控除
- 10年以上所有していた場合の軽減税率の特例
「居住用財産の3,000万円特別控除」は、自宅を売却した際の譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。長年住んだ家を売る際に適用され、売却益にかかる譲渡所得税の負担を軽減できます。
「10年以上所有していた場合の軽減税率の特例」は、親が10年以上住んでいた自宅を売却する場合、譲渡益にかかる税率が通常よりも軽くなります。「居住用財産の3,000万円特別控除」との併用が可能です。
相続が発生する前に空き家を処分することには、以下のメリットがあります。
- 現金化して老後資金を増やせる
- 節税のために活用できる特例がある
- 現金で分割しやすく相続時のトラブルになりにくい
- 子どもが空き家の処分に悩まずに済む
ただし、相続前に売却する場合には注意点もあります。相続税の課税対象が現金になるため、小規模宅地の特例など不動産の優遇措置は受けられません。また、次の住まいを賃貸で探す場合は、賃貸の審査が通りにくいなどのリスクがあります。
相続税とのバランスや住まいの確保といったデメリットもあるため、売却を検討する際は税理士や不動産の専門家と早めに相談するのが安心です。
空き家を相続する際の注意点

相続してから慌てて対応するのではなく、事前に知っておきたいポイントがいくつかあります。
- 安易に解体して空き地にしない
- 放置すると税金が高くなる可能性がある
- 名義変更しないと罰則がある?
- 適用できる制度を把握しておく
ここでは、空き家を相続する際に押さえておきたい注意点をわかりやすく解説します。
安易に解体して空き地にしない
空き家を更地にするには、木造住宅では一般的に100万〜200万円前後が目安の解体費用がかかります。解体後はすぐ売却できるとは限らず、費用がかかって税金も上がるというケースが考えられます。
空き家を解体してしまうと、住宅用地の特例が適用されず固定資産税が最大で6倍になる可能性があります。また、相続した土地が市街化調整区域や法規制のエリアにあると、建て替えが制限されます。
空き家を相続した際は、建物付きで売却や賃貸ができないかを優先して検討しましょう。リフォームやリノベーションによって活用できるケースもあり、手を加えることで買い手や借り手が見つかる可能性もあります。
放置すると税金が高くなる可能性がある
老朽化した空き家を何も手を加えずに放置していると、特定空き家に指定される可能性があります。倒壊の危険があったり、ゴミがたまって衛生的に問題があったりするなど、周囲に悪影響を与える状態にある空き家に対して、行政が下す判断です。
特定空家に指定されると、所有者に修繕や解体などの指導・勧告・命令が行われ、従わなければ最大50万円の過料が科されることもあります。特定空き家に指定されると軽減措置である「住宅用地の特例」が適用されなくなり、固定資産税が最大6倍に増額される恐れがあります。
特定空き家に指定される前に、適切な管理や売却の検討を早めに行うことが結果的に大きな出費を防ぐ節税対策になります。
名義変更しないと罰則がある?
これまでは義務ではなかった相続登記ですが、2024年4月1日から法改正により義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記を行わないと、最大10万円の過料が科される可能性があるため注意が必要です。
名義を変更しないままにしておくと、以下のようなリスクがあります。
- 不動産の共有者が増える
- 空き家の売却・賃貸・解体ができない
- 特定空き家に指定されるリスクが高まる
名義変更しないで放置すると、相続人の一人が亡くなったら権利関係がさらに複雑になり、分割や売却が難しくなります。空き家の管理が行き届かなくなり、劣化が進行すれば行政から勧告や命令を受ける可能性もあります。
空き家を相続した際は、相続登記で名義変更を早めに済ませることが重要です。手続きは自分でも可能ですが、司法書士に依頼すれば数万円程度の報酬で対応してもらえます。
相続の登記についてはこちらの記事「空き家を相続したら要注意!登記の義務化と管理リスクを回避するポイントを解説」も参考にしてください。
適用できる制度を把握しておく
空き家の相続では、適用できる制度を把握しておくことが大きな節税や負担軽減につながります。制度を知らずに放置すると、本来受けられるはずだった控除や特例を逃してしまい、余分な税金や維持費を支払うことになるかもしれません。
以下に、空き家相続時に活用できる主な制度を紹介します。
- 小規模宅地等の特例|相続税を最大80%軽減
- 売却時の3,000万円控除|売却時の譲渡所得を軽減
- 相続土地国庫帰属制度|不要な土地を国へ引き渡す
相続土地国庫帰属制度は2023年4月から始まった制度で、どうしても使う予定がない不要な土地を国に引き取ってもらう制度です。審査に通れば国に所有権を移せますが、要件や手続きが複雑なため、専門家に相談するとスムーズです。
空き家を相続する際に利用できる制度は複数ありますが、知らなければ活用できません。制度の適用には期限や条件があるため、早めに調べ、必要に応じて専門家の力を借りることが大切です。
まとめ:空き家の相続では税金対策できる制度を活用しよう
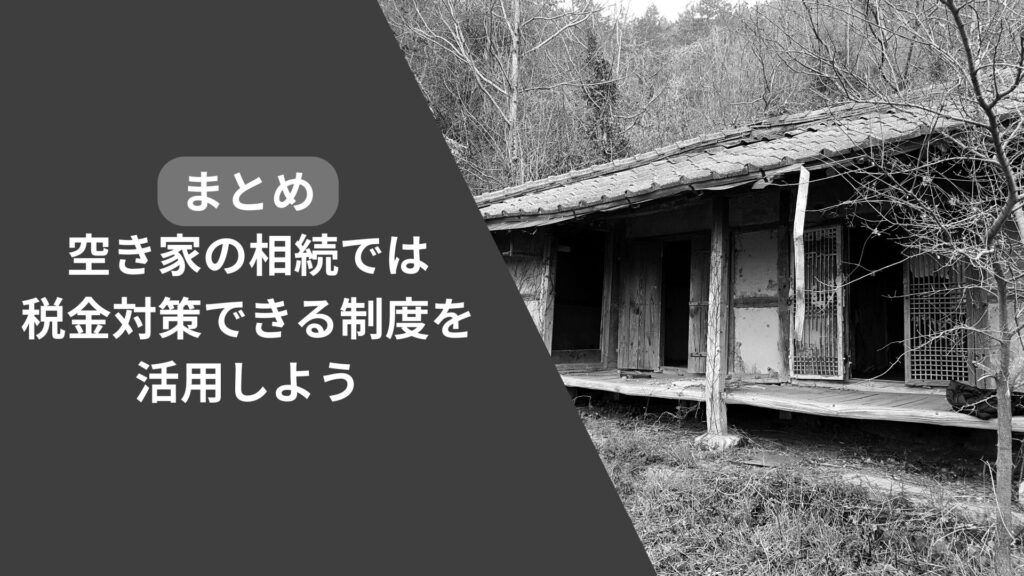
空き家を相続すると、さまざまな税金の納税が避けられません。しかし、小規模宅地等の特例や、空き家売却時の3,000万円控除などの制度をうまく活用すれば、相続税の節税が可能です。相続前に売却するという選択肢も含め、状況に応じた対策をとることが重要です。
相続登記の義務化や特定空き家のリスクなど、対応を後回しにすると罰則や高額な税負担につながる可能性があります。空き家は「所有しているだけ」でコストが増え資産価値も下がるため、早めの判断と対応が重要です。